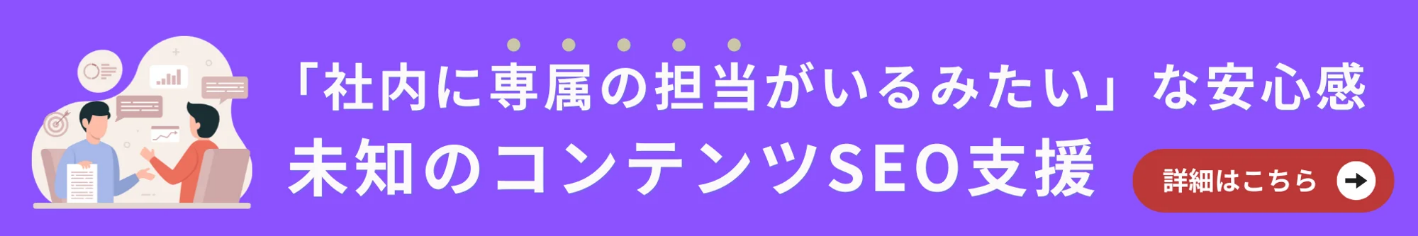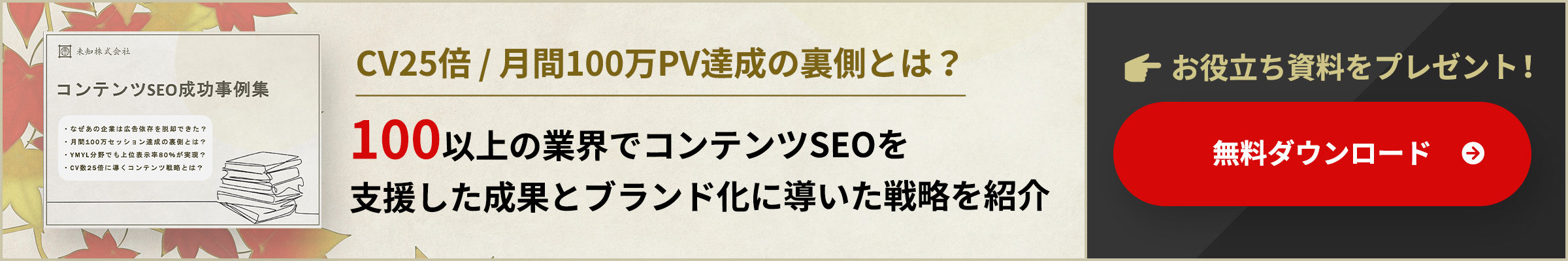SEO記事とは
SEO記事とは、検索エンジン最適化を目的に作成された記事のことです。別名「コンテンツSEO」とも呼ばれ、主にGoogleなどの検索エンジンで上位に表示されることを目的に、特定のキーワードやフレーズを適切に使い、ユーザーにとって有益な情報を記事化します。
現在、SEO記事はコンテンツマーケティングの中でも主流の施策となっており、多くの企業でSEO記事は、今やコンテンツマーケティングの中でも主流になっており、多くの企業がSEOを目的にした記事制作を積極的に行っています。
とはいえ、検索結果の上位に表示される記事を作成することは決して簡単ではありません。たまたま上位に表示されることはあっても、安定して継続的に上位表示を目指すのは、十分なSEOの知識が必要になります。
上位表示されるSEO記事を作成するためには、検索エンジンがどのような記事を評価するのか、その評価基準を理解した上でコンテンツを作成することが重要です。
SEOに強い記事が満たしている評価基準
検索エンジンから評価を得て上位表示されるSEO記事には、いくつかの共通した傾向があります。
代表的な検索エンジンであるGoogleは、そのアルゴリズムを重視した施策を取り入れることが不可欠ですが、実際に「記事=Webページ」のどういう部分を評価しているのか、詳細な情報は公開されていません。
Googleは、順位上昇につながる基準を明確には開示していないものの、アルゴリズムから評価されやすい重要な項目を「Googleガイドライン」などで発表しています。これらのガイドラインを参考にすることで、検索エンジンが評価する基準を理解することができます。
検索エンジンに評価されやすい記事を書くためにも、まずは検索エンジンのアルゴリズムの評価基準を確認しましょう。
主に評価されるポイントを紹介します。
ユーザビリティを重視したサイト構造
ユーザビリティ(使いやすさ)を重視したサイト構造の改善は、検索エンジンのクローラーによる巡回を促す重要な施策です。例えば、ページ1に関連性の高いページ2が適切につながっていれば、ユーザーはウェブサイト内を回遊しやすくなります。
内部リンク周辺に補足説明があるなど、ユーザーにとって回遊しやすいサイト構造は、クローラーにとっても構造や中身を理解しやすく、ページの高評価につながります。
Googleはユーザーの利便性を重視しているため、サイト構造はもちろんコンテンツの質やコーディングも重要です。
検索意図に沿ったコンテンツ
特にGoogleは「ユーザー第一」を心がけており、Googleが掲げる10の事実からも記されています。
1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
2.1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
3.遅いより速いほうがいい。
4.ウェブ上の民主主義は機能する。
5.情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。
7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。
8. 情報のニーズはすべての国境を越える。
9. スーツを着なくても真剣に仕事はできる。
10. 「すばらしい」では足りない。
SEOに強い記事を作成する際、重要なのはユーザーの検索意図に沿った情報になっているかが重要なポイントです。もしユーザーが求めている情報が含まれていなければ、その記事は閲覧されず、検索エンジンからも評価されにくくなります。
SEOに強い記事を作成する際、ユーザーの検索意図に沿った内容になっているかが重要なポイントのひとつです。知りたい情報が含まれていなければ閲覧されず、ユーザーにとって価値のないコンテンツとして検索エンジンからの評価が低くなるためです。
ユーザーの検索意図を正しく理解し、必要な情報をしっかりと網羅することが求められます。検索意図を分析する際には、「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」を意識することが重要です。
顕在ニーズ
顕在ニーズとは、ユーザーが明確に自覚している悩みや課題のことです。例えば、「ダイエット方法を知りたい」「SEO対策を改善したい」といった具体的な問題を抱えているユーザーが検索する内容です。
この悩みに応えるためには、ユーザーが知りたい具体的な情報をキャッチアップして、問題解決に直結する内容を提供することが重要です。
潜在ニーズ
潜在ニーズは、ユーザーが自覚していない欲求であり、満たされることで理想の状態が叶えられるものです。
例えば、「SEO対策に強いサイトを作りたい」という願望があるユーザーは、具体的にどのようにSEOを改善すれば良いかはわかっていないことが多いです。
このような潜在ニーズに対応するためには、ユーザーが理想とする結果に導けるようなアドバイスや情報を提供し、検索しただけでは得られなかった新たな視点や解決策を提示することが求められます。
適切なコーディングが必要
検索エンジンからの評価を受けるには、SEO記事の内容を検索エンジンに正しく理解してもらう必要があります。そのためには、検索エンジン向けの適切なコーディングを行うことが大切です。
検索エンジンはウェブサイトに設定されたタグなどから、詳細な内容を読み取っています。ウェブサイトの内容を示すための代表的なタグは「titleタグ」「metaタグ」「hタグ」などです。
| SEO記事によく使うタグ | 詳細 |
| titleタグ | ・ページタイトルを指定するタグ ・検索結果ページやブラウザのタブに表示される ・該当ページが何のページなのかを検索エンジンやユーザーに伝える |
| metaタグ | ・ウェブページの説明文や文字コード、ページの表示の広さなどを指定するタグで、複数の種類がある ・検索画面でウェブページの概要説明をしたり、文字コードの指定により文字化け対策をしたりできる |
| hタグ | ・ページの見出しを指定するタグ ・h1からh6までのタグを記述して、ページ内の階層構造を検索エンジンに伝えられる |
なお、Googleのウェブマスター向けガイドラインでは「Googleがサポートしているmetaタグ」一覧を確認できます。
検索結果で上位表示されるよう、コーディングを漏れなく行い、ウェブサイトを適切に読み取らせる環境を整えましょう。
外部サイトからの評価
外部の動向も、評価に影響する可能性があります。代表的な外部施策が被リンクの獲得です。第三者のウェブサイトから自社サイトへのリンクを多く設置してもらうと、検索エンジンの評価に影響します。
ただし、すべての外部リンクが望ましい影響を与えるとは限りません。被リンクは良質と悪質(低品質)な2種類に分けられます。
| ・良質な被リンク:信頼性の高いウェブサイトからの被リンク ・悪質(低品質)な被リンク:スパムリンクなど |
2000年代、検索エンジンにおけるアルゴリズムの精度が低かったころは、単純な被リンクの数で上位表示を狙うことができました。
被リンクを専門会社から購入したり、自社で制作した他サイトからリンクを設置したりと、当時は悪質な自作自演が横行したため、低品質なコンテンツが多く上位表示されていました。
現在は、検索エンジンがユーザビリティ重視に方向転換した影響もあり、悪質な被リンクの自作自演では上位表示を狙いにくくなっています。検索順位を上げるためには、信頼性の高いウェブサイトからの自然な形でのリンクを獲得する必要があります。
また、サイト外部の評価要素には、被リンクのほかにサイテーションもあげられます。自社アカウントのSNSを活用するなど、積極的にサイテーション獲得を狙いましょう。
【6step!】SEOに強い記事の作り方
検索上位を目指すには、内容と構造の両方でSEOに強い記事を作成することが重要です。検索エンジンの評価基準を意識して、高品質でユーザーにとって利便性の高いコンテンツに仕上げましょう。
ここからは、SEO記事を書くときの主な流れと注意点を解説します。
【キーワード】SEO記事から得たいゴールを決める
SEO記事を作成する際は、まずその記事を作成することでどうなりたいかの目的設定が重要です。「コンバージョンにつなげたい」「流入数を増やしたい」など、目的によって選定すべきキーワードや記事の方向性が変わるためです。
コンバージョンにつなげたい場合は、すでに購買意欲があるユーザーをターゲットにして、ニーズに応えるキーワードを選定する必要があります。例えば、ピラティスの事業を展開する企業のサイトであれば「ピラティス 費用」「ピラティス おすすめ」などです。
一方、認知拡大や流入数増加を目指す場合、商品やサービスに興味をもつきっかけとなる悩みの解決策など、潜在層のニーズを満たすコンテンツの作成が望ましいです。ピラティスがテーマの場合、「姿勢を良くする習慣」「体型維持 方法」などがキーワードの候補として考えられます。
その際、ビッグキーワード(検索エンジンで多くのユーザーが検索するキーワードのこと)で上位表示できれば、より多くのユーザーの目に触れるようになります。
【ターゲット】キーワードを検索するユーザーの意図を考え抜く
ユーザーがどのような意図でそのキーワードを入力したのか推測して、ニーズに応えられる情報を盛り込んだ記事を目指しましょう。Googleが重視しているユーザーの利便性とは、検索者が検索した目的に応じたウェブサイトやページをユーザーに提供することです。
検索意図を探る方法は、以下のように複数あります。
検索結果の競合サイトを参考にする
狙っているキーワードを検索窓に入力して、現時点でどのようなウェブサイトが上位表示されているのか確認する方法です。競合となるウェブサイトから、ユーザーが求めている情報や評価されやすいウェブサイトを推測できます。
競合サイトを分析する際は、競合サイトが使用しているキーワードや見出しのほか、共起語も参考になります。
共起語とは、特定のキーワードと一緒に使われやすい単語です。競合サイトが多く使用していることから、ユーザーの検索意図を満たすために必要な要素だと考えられます。ラッコキーワードなどのツールを活用すると簡単に抽出できます。
ただし、共起語の盛り込みを目的化すると読みにくくなる場合があるため、あくまでユーザーニーズを把握する手がかりとして使うことが重要です。
検索エンジンのアルゴリズムはアップデートを繰り返しており、以前よりも上位表示されるウェブサイトの質が向上しています。競合の傾向を学び、自社サイトに落とし込むべき具体的なテーマやキーワードを探る方法として、検索結果の参照は効果的です。
サジェストキーワードを確認する
キーワードの組み合わせをもとに、ユーザーの検索意図を探る方法もあります。たとえば、サジェストキーワードは、検索窓に入力されたキーワードと関連性の高い内容が推測され、表示される仕組みです。
サジェストキーワードは、入力したキーワードと実際に組み合わせて使用されることが多いものを候補として表示されています。
活用するときは表示された各サジェストキーワードを一覧化して、精査しましょう。狙っているユーザー層の検索意図に沿ったサジェストキーワードか、振り分けたうえで活用します。
キーワードから判断できない場合は、実際に検索して上位表示されたウェブサイトを確認する方法がおすすめです。コンテンツ内容が自社の想定しているユーザー層や検索意図にマッチしていれば、記事に盛り込むべきサジェストキーワードといえます。
ただし、必ずしもすべてのサジェストキーワードがひとつの検索意図に沿っているとは限りません。関連するキーワードを予測するための材料に、検索した本人の過去の入力内容も含まれているためです。
自社サイトの担当者が、普段仕事で使用しているデバイスでサジェストキーワードを調べようとすれば、過去の入力内容が表示されるため、サジェストキーワードに影響します。結果、ターゲットユーザーの検索意図にまったく沿わない内容も含まれます。
■関連キーワードを確認する
サジェストキーワードを振り分けるときは、関連キーワードもあわせて整理しましょう。関連キーワードとは、検索窓に入力されたキーワードと関連性のあるもの、または関連すると予測されるキーワードです。
サジェストキーワードとの違いは、表示内容が検索者本人の過去の動向に左右されないことです。関連キーワードは、共起語や関連サイトなどウェブ上のデータから抽出されます。
検索窓に入力したメインキーワードと関連して、一般的に使用されることの多いキーワードが表示される仕組みです。Googleユーザーの動向にもとづいた一覧のため、検索意図を知る重大な手がかりとなります。
関連キーワードを調べるときは、ツールの活用がおすすめです。ラッコキーワードやGoogleキーワードプランナーなど無料のツールでも十分役立つので、効率的に関連キーワードを取得しましょう。
【記事構成】読みやすさを意識した構成を作成
記事構成を作成する際は、ユーザーへの伝わりやすさを考え抜いた見出しや階層構造にすることが大切です。
まず、ユーザーニーズを意識して、求める情報を記事の前半に配置する必要があります。知りたい情報がなかなか出てこないと、ユーザーは離脱してしまうためです。その上で、より具体的で詳しい情報やプラスで知っておくと役立つ情報などを順に配置していきましょう。
例えば、以下のような流れにするとユーザーの疑問がスムーズに解消されます。
| 検索キーワード | 引っ越し 時期 |
| 1.ユーザーが求める情報 | お手頃な費用で引っ越しが出来る時期は何月ごろか |
| 2.具体的でより詳しい情報 | なぜその時期が引っ越しに向いているのか(繁忙期・閑散期の引っ越し費用、物件数など) |
| 3.補足や知っておくと役に立つ情報 | 引っ越しで後悔しないためのポイント(費用を抑える方法、満足する物件を探す方法など) |
また、見出しにキーワードを含めると、どのような内容なのかがユーザーに伝わりやすくなります。ユーザーは見出しを見て、記事に自分の知りたい情報があるかを判断するため、一目で概要が伝わるような見出しを心掛けましょう。
そのほか、見出しの親子構造を無視しないこともSEOにおいて重要なポイントです。h2の次に来る見出しは、h2またはh3とします。h3を飛ばしてh2の直下にh4が入るなど、見出しの親子構造を崩さないよう注意してください。
【競合調査】すでに上位にある記事が拾いきれていない点を追加する
競合との差別化をはかるためには、ほかのウェブサイトがカバーできていない情報を盛り込むことが重要です。狙っているキーワードで検索して、すでに上位表示されている記事を確認してみましょう。
上位表示の記事でも、ユーザーが満足する内容を完全には提供できていない場合があります。再検索ワードが分かれば、上位の記事が拾いきれていないニーズを見つけられ、自社のコンテンツに盛り込めます。
再検索ワードを調べるときは、特別なツールは必要ありません。検索結果に表示される『他の人はこちらも質問』の枠に表示されたキーワードが、再検索キーワードと判断できます。
ユーザーがどのような課題を解決できていないか把握し、補足できる見出しを自社のコンテンツに加えれば、競合との差別化が可能です。
【記事執筆】正確なデータを基に記事の作成を行う
記事の信頼性を向上させるために、調査データを使用することがあります。データを使用するときは、正確かどうかを入念に確認してから取り入れましょう。
例えば、官公庁が公表しているデータや、新聞社、書籍、調査機関のプレスリリースなどがデータ参照元として適切です。ただし公的機関以外からの引用は、事前連絡が必要などルールが設けられている場合がある点に注意してください。
また、あくまで公開されている情報かつ、引用の範囲に留めた使用であるべきです。広範囲の引用は常識的とはいえず、検索エンジンからもコピーコンテンツと判断される恐れがあります。引用であると分かるよう、引用元の明記も必要です。
データを引用するときは競合から流用するのではなく、必ず一次資料(データを公開しているメディア)の情報を参照することも、トラブルを避けるコツです。
【入稿】ユーザーが閲覧しやすくなるよう工夫する
良質な記事は、ユーザーにとって見やすいかどうかも重要です。
仮に競合サイトにない情報が豊富に掲載されていたとして、画面いっぱいに改行すらない長文が掲載されていたら、最後まで読むユーザーは多くありません。インターネットで情報検索するユーザーのなかには、情報取得の手軽さを重視している層も含まれるためです。
改行や文字の大きさ、フォント、装飾など、ターゲットユーザーがストレスなく読めるよう配慮する必要があります。
また、文章だけで理解しにくい場合は、オリジナルの図解・写真や表などを積極的に活用しましょう。記事の可読性が向上し、ユーザーが最後まで読む可能性が高まります。
なかでもオリジナルの画像を使用することで、ユーザーの理解度が上がるだけでなく、記事の独自性として検索エンジンからも評価されます。画像を挿入すれば、画像検索からの流入を見込めるようになるのもメリットです。
SEO記事を作るときに注目すべきポイント
SEOの施策で最も重視されるのが、コンテンツの質です。良質なコンテンツは被リンクを獲得しやすく、ユーザーのサイト回遊を促します。
コンテンツの質を向上させるためには、記事の作成方法を見直しましょう。優良な記事でコンテンツが高品質になれば、SEOにも強くなります。
「SEOに強い=すなわち高品質な記事」を作成するためには、5つのポイントが重要です。
| 1.E-E-A-Tを意識した自社ならではの記事かどうか 2.内部リンクが最適化されているか 3.記事に適した構造化データになっているか 4.どのデバイスでも見やすいサイトデザインになっているか 5.ページの読み込み速度に問題はないか |
E-E-A-Tを意識した自社ならではの記事かどうか
Googleは、コンテンツ内容に高い専門性があり、ウェブサイトや記事作成者に権威性や信頼性があると、ユーザーにとって有用なコンテンツと判断して高い評価を与える傾向があります。
E-E-A-Tとは、下記のとおり4つの要素を表す言葉です。
・Experience(経験)
・Expertise(専門性)
・Authoritativeness(権威性)
・Trustworthy(信頼性)
E-E-A-Tを意識したコンテンツの作成にあたって注意すべきポイントは、社会的な地位や資格、サイト運営者の企業規模のみが評価されるわけではないことです。
E-E-A-Tそれぞれの重視されるポイントは次のとおりです。
Experience(経験)
記事のテーマに関する経験や体験に基づく記載を入れると、高品質なコンテンツとして評価されやすくなります。他サイトには再現できない独自性の高い記事になるためです。
Experience(経験)にあたる記載には、記事を作成した本人の実体験や顧客の体験談・レビューなどがあげられます。
例えば、商品やサービスをおすすめする記事を作成する際、執筆者が実際に使用した体験談を添えると、商品の魅力を伝える際の信憑性が高まります。
同様に、商品を使用した人々のレビューがあれば、ユーザー目線の意見として参考にされ、商品のイメージアップにつながるでしょう。
Expertise(専門性)
記事に取り上げられている内容について、作成者が専門家と判断されることが評価軸に影響します。必ずしも資格保有者や関連する職業の人物が専門家とは限りません。例えば、個人が運営しているコンビニアイスの評論サイトがあります。
類似サイトは複数あり、いずれもウェブサイト運営者は特別な資格者ではない点が共通しています。単純にコンビニアイスが好きで年間多く食べている人が、個人の評論をまとめているだけの口コミサイトですが、検索上位の常連となっています。
評論サイトの例からも分かるように、コンテンツ内容によっては、運営者や記事執筆者が資格を有する専門家となる必要はありません。特定のトピックに詳しい人物が、専門家と判断されます。
ただし医学や薬学など、具体的な情報やアドバイスを提供する場合は、医師や看護師といった有資格者の執筆や監修が重視されます。ウェブサイトやページの専門性を向上させるためには、コンテンツに合った専門性の確保が重要です。必要であれば、有資格者への監修を検討しましょう。
Authoritativeness(権威性)
権威性とは、ウェブサイト運営者や記事作成者が、特定の分野において専門性を有すると認められていることです。前述の個人によるコンビニアイスの口コミサイトも、上位表示されていることから、権威性があるといえます。
同じ情報量で同じデザインのコンテンツを作成した場合、権威性の高いウェブサイトの方が上位に表示される可能性があります。権威性が低い(社会的に知名度の低い)個人や企業が作成したコンテンツは、信頼性が低いと判断されやすいためです。
知名度の低い個人や企業が高い権威性を得る方法は、良質な被リンクを獲得するなどです。大手企業や公的なサイトなどの権威があるウェブサイトからのリンクを多く得られれば、有益なコンテンツと認識されます。
Trustworthy(信頼性)
信頼性には、ウェブサイトのみならず、運営者も含まれます。著名な専門医が実名と顔写真を出して書いている記事と、匿名で医師を自称している人物が書いた記事を比較すると、多くのユーザーが前者の方を信頼できると判断しがちです。
個人や社会的知名度の低い企業がウェブサイトの信頼性を高めるためには、最低限、運営者やライターの情報を正しく記載する必要があります。
内部リンクが最適化されているか
自社サイトで公開したSEO記事は、内部リンクを整備することでユーザビリティが向上し、検索エンジンからの評価向上にもつながります。検索エンジンのクローラーは、ウェブサイト内の内部リンクをたどってクロールするためです。
内部リンクを設置する際は、導線を引くように関連ページへつなげることが大切です。例えば「夏バテの予防方法」の記事から「熱中症対策グッズおすすめ5選」の記事へ誘導すると、ユーザーの悩みを段階的に解決しつつ商品をスムーズに訴求できます。
また、内部リンクを設置する際には、リンク先の内容を示すアンカーテキストの記載が重要です。リンク先の情報に関するキーワードを含んだテキストにすると、ユーザーや検索エンジンに内容が伝わりやすくなり、クリック率やSEO効果が高まります。
記事に適した構造化データになっているか
検索エンジンに自社サイトの情報を伝える手段として、構造化データの確認・改善もあげられます。
ウェブサイトに関する情報を規定のルールにしたがって記述したデータのことです。
最適な記述を行うと、ウェブサイトの情報が検索エンジンに正確に伝わります。
例えば、人物データを掲載するとき、通常のテキストだけでは検索エンジンは「そこにテキストがある」ことしか分かりません。Aさんの名前を記載しても、検索エンジンは人物名であることを理解できず、テキストデータと認識します。
Aさんの名前が人物名であることを伝えるためには、構造化データで『”name”:』をもちいて説明しなくてはなりません。構造化データが正しく記述されていれば、検索エンジンはテキストとしてではなく、「Aは人物名である」と込められた意味も含めて認識してくれます。
ウェブサイトやページにどのような内容が記載されているのか認識されることで、品質の良い記事も評価されやすくなります。
また、コンテンツによってはリッチリザルトに表示されやすくなる点も、構造化データ活用のメリットです。
検索結果の上部にひときわ目立つようにウェブサイトやページが表示されることです。
競合サイトよりも目立ち、ユーザーのクリックを誘導しやすくなります。 リッチリザルトを獲得するためにも、記事内容に適した構造化データの記述を心掛けましょう。
どのデバイスでも見やすいサイトデザインになっているか
ユーザーはPCだけでなくさまざまなデバイスを利用してウェブサイトを閲覧するため、モバイルフレンドリーの意識が重要です。モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットなどモバイルを使用するユーザーが閲覧しやすいサイトデザインを取り入れることです。
スマートフォンやタブレットなどからのアクセスが多いウェブサイトは、PCではなくモバイル閲覧を想定したデザイン・設定を取り入れる必要があります。既存のPC用サイトを利用したい場合は、metaタグのビューポート設定が欠かせません。
ビューポート(viewport)とは、ウェブサイトをどの大きさで表示するのかを設定するmetaタグのこと。
タグを記述するときは、PCとモバイルで設定が異なる点に注意しましょう。
PC用をあえて設定する必要はありませんが、モバイル用は忘れず設定しておくことをおすすめします。
ビューポートは横幅や縦幅など、さまざまな表示サイズを設定できます。一部のスマートフォンは設定が反映されないことがあるため、具体的な数字を入力するよりも「デバイスごとに最適化する」設定が適切です。
デバイスに合わせて自動で最適化してくれるビューポートの設定は、下記のとおりです。Googleでも使用されているオーソドックスな設定です。一部のスマートフォンと相性が悪くても表示の問題が生じにくい特徴があります。
タグの設定後は、必ず実際のモバイル端末を使用して正常に表示されるか確認しましょう。
ページの読み込み速度に問題はないか
ページの読み込み速度の遅さは、ユーザーにストレスを与える要素のひとつです。クリックしたウェブサイトが表示されなければ、情報取得を急いでいるユーザーは直帰する可能性が高くなります。
また、モバイルユーザーは通信環境が整っていない外出先でウェブサイトにアクセスすることもある点を考慮すべきです。ページの読み込みが早いウェブサイトなら、通信環境が安定しにくい場所でも表示されやすくなり、ユーザーはストレスフリーで閲覧できます。
Googleのガイドラインにもページ読み込み速度は重要と記されています。検索エンジンのアルゴリズムも、モバイル端末によるページの表示速度を評価するようアップデート(Speed Update)されました。
自社サイトのページ読み込み速度は、Google AnalyticsまたはGoogle PageSpeed Insightsで確認可能です。Google PageSpeed Insightsはスコアだけではなく、悪影響を与えている(スコアを下げている)問題点を赤字表示してくれます。
ページ読み込み速度の改善策には、ブラウザキャッシュの活用、ソースコード軽量化や画像の最適化などがあります。AMP(Accelerated Mobile Pages)を実装して、Googleにページ情報をキャッシュしてもらう方法も効果的です。
まとめ
SEO施策の目的は、ウェブサイトやページを検索結果に上位表示させ、集客や購入などのコンバージョンにつなげることです。必ずしも特定のキーワードで1位表示を狙う必要はありませんが、クリック率を少しでも上げるためには、可能な限り上位を目指しましょう。
検索エンジンから評価され、上位表示されるためには、質の良い記事の作成が欠かせません。SEOに強い記事を作成し、本コラムで解説したモバイルフレンドリー化などユーザビリティ向上も行えば、集客力向上が期待できます。
社内でSEOに強い記事を作成するのは困難と感じたら、外注する選択肢もあります。未知株式会社ではSEO施策も含めてご相談いただけますので、ぜひ一度お悩みをお聞かせください。