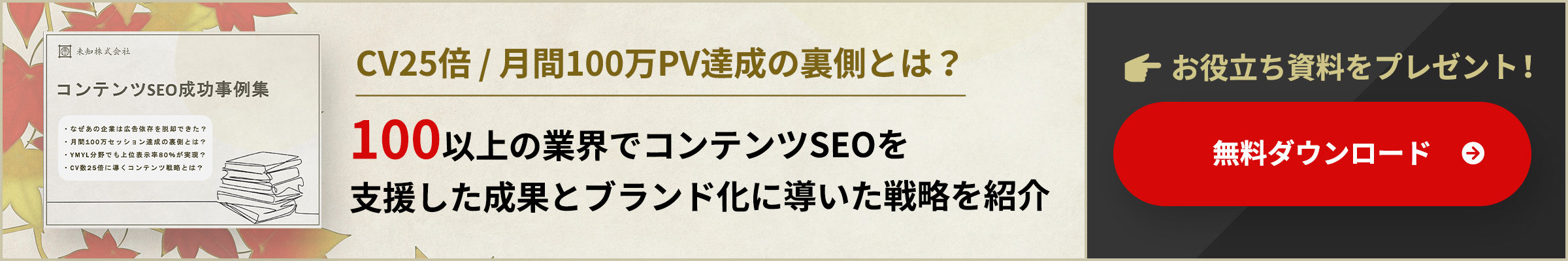目次
コンテンツ制作とは
コンテンツ制作とは、特定の目的やターゲットに向けて情報を企画・作成し、さまざまな形で発信するプロセスを指します。
コンテンツには、Webサイトの記事、SNS投稿、YouTube動画、デザイン性の高い広告画像など、さまざまな形式があります。これらのコンテンツは、企業の認知度を高めたり、見込み顧客のリード獲得に貢献したり、既存顧客との関係性を強化したりするために活用されています。
コンテンツ制作が重視される背景
現在、Webマーケティングが主流となる中で、コンテンツ制作はその中心的な役割を果たしています。
従来型の有料広告は、商品やサービスそのものを直接訴求することを目的としています。しかし、広告ブロックアプリの普及に象徴されるように、ユーザーの意思に関係なく表示される広告は、受け手にとって押し付けがましく感じられることも少なくありません。
統計データプラットフォーム「スタティスタ」の調査では、『広告ブロッカー』の使用率は2014年の15.7%から2021年では27%増加していることを報告しています。
こうした背景から、広告だけに頼らないWeb集客手法が注目されるようになりました。
コンテンツはユーザーが自身で情報を探し、主体的に選び取る形で接触するため、広告と比較して自然に受け入れられる傾向があります。
このように、企業が価値ある情報を発信し、ユーザーとの信頼関係を築きながら最終的に成約へとつなげる手法は、コンテンツマーケティングとして普及されました。
デジタル時代の現在、情報過多の中で他との差別化を図るには、ユーザーが求める価値あるコンテンツを適切なタイミングで届けることがますます重要になっています。
コンテンツの種類と制作のポイント
この「コンテンツ」には、記事、動画、SNS投稿、ホワイトペーパー、など、幅広い種類があります。それぞれの媒体や形式に応じて、ターゲットやコンテンツ内容は異なります。
ここでは、コンテンツ制作を始めるうえで、押さえておきたいコンテンツの種類について紹介します。
記事コンテンツ
記事コンテンツは、オウンドメディアやブログなど、自社が運営するWebメディアを通じて公開されるテキストベースのコンテンツです。ユーザーが検索エンジンやSNS経由でアクセスしやすい特性があり、認知度の向上やリード獲得において重要な役割を果たします。
また、現代のWebマーケティングにおいて、記事コンテンツは特に重要な役割があります。SEOを施した記事を公開することで、検索結果の上位に自社のページが表示され、見込み顧客の流入を期待できます。
初期費用や広告費を抑えて始められるため、リソースを効率的に活用しながら長期的な効果を狙うことができます。
記事コンテンツのメリット
| 1.長期的な流入の確保 | SEO対策を施した記事は、検索結果の上位に表示されやすく、継続的な流入が期待できます。 |
| 2.専門性の訴求 | ユーザーに有益な情報を提供することで、企業の専門性や信頼性を高めることが可能です。 |
| 3.低コストの集客 | 記事コンテンツは初期費用が抑えられる一方で、長期的な集客効果を期待できます。 |
記事におけるコンテンツ制作のポイント
オウンドメディアやブログなどの記事を制作する時は、ユーザーの視点に立ち、課題やニーズを深く理解したうえで、情報を的確に届けることが求められます。以下のポイントを意識しましょう。
| ターゲティング | SEO対策を施した記事は、検索結果の上位に表示されやすく、継続的な流入が期待できます。 |
| テーマとキーワードの方針 | ユーザーが検索しやすいテーマやキーワードを選び、記事内容に適切に組み込む。 |
| 読みやすい構成 | 目次や見出しを活用して情報を整理し、ユーザーが欲しい情報に素早くアクセスできるようにする。 |
| カテゴリ設定 | 関連する記事を整理し、ユーザーがサイト内を回遊しやすい構造を作る。 |
動画投稿
動画コンテンツは、音声と映像を組み合わせて情報を伝える形式のコンテンツで、テキストよりも多くの情報を短時間で視聴者に伝えることができるのが特徴です。
最近では、企業のマーケティング活動において動画コンテンツの重要性がますます高まっており、多くの企業が自社のYouTubeチャンネルを開設し、積極的に活用しています。
従来のテキストベースのコンテンツでは伝えにくかった情報を、動画では視覚や聴覚を通じて分かりやすく発信できます。
例えば、商品の使用方法や専門的なノウハウ、ユーザーの声などを動画にすることで、テキストだけでは伝えきれない微妙なニュアンスやリアリティを視聴者に届けることができます。その他の活用例は以下です。
動画コンテンツの活用例
| 商品・サービス紹介動画 | 商品の使い方や特徴を具体的に示すことで、購入を検討しているユーザーの理解を深め、購買意欲を高めます。 |
| セミナーやイベントの紹介動画 | 実際のセミナーの雰囲気や内容を動画で伝えることで、参加を促進します。特にBtoBの分野では、専門性の高い情報発信に適しています。 |
| インタビューや事例紹介 | 実際のユーザーの声や成功事例を動画で紹介することで、視聴者にリアルな説得力を与えます。 |
| ノウハウやハウツー動画 | 実務的なスキルや知識を伝える動画は、視聴者に有益な情報を提供し、ブランドの専門性をアピールします。 |
動画コンテンツの注意点
効果的な動画コンテンツを制作するためには、視聴者の興味やニーズに合った内容を考えることが重要です。また、映像のクオリティや編集の工夫がコンテンツの価値を大きく左右します。さらに、動画を適切なプラットフォームで配信し、視聴者の反応を分析することも欠かせません。
動画コンテンツは、商品の紹介だけでなく、ユーザーとの信頼関係を構築し、エンゲージメントを高めるための強力なツールとして、今後もその活用の幅を広げていくでしょう。
SNS
コンテンツ制作において、ユーザーとの接点を増やし、企業のコンセプトを効果的に伝えるためには、SNSの活用が欠かせません。
X(旧:Twitter)やFacebook、Instagramといったプラットフォームは、多くのユーザーが日常的に利用しており、企業が情報発信を行ううえで非常に有効な手段です。
特徴はテキスト、画像、動画など、多様な形式のコンテンツを活用できる柔軟性があげられます。
また、自社のWebサイトやオウンドメディアと連動させることで、より広範囲なユーザーにリーチしやすくなります。
ソーシャルメディアの普及によりSNS活用が浸透しています。まだまだ概要が不明な方もいるかもしれません。主なメリットは以下です。
SNS投稿のメリット
| 1.ブランディング向上 | 定期的な投稿を通じて、企業の世界観や価値観をユーザーに浸透させることができます。 |
| 2.エンゲージメント強化 | コメントやシェア、いいねといったユーザーとの双方向のやり取りを通じて、関係性を深められます。 |
| 3.リアルタイム性 | 新製品のリリースやキャンペーン情報を即座に発信できるため、ユーザーの関心を効率的に引きつけます。 |
SNS投稿の注意点
SNSコンテンツを制作するうえで、プラットフォームごとに異なる特性を理解し、適切なトーンやフォーマットを採用することが重要です。また、投稿頻度やタイミング、ユーザーからの反応に応じた柔軟な対応も求められます。
メルマガ・ニュースレター
メルマガ(メールマガジン)やニュースレターは、企業の情報やサービスを定期的に配信する効果的なコンテンツ形式の一つです。購読者の多くは、自ら登録を行う主体的なユーザーであり、自社のサービスや製品に高い関心を持つ見込み顧客や既存顧客が中心です。
また、登録者の属性(性別、年代、居住地、購入履歴など)に基づいてセグメントを行い、個別化された情報を配信することで、より高い効果が期待できます。
これだけだと、あまりピンとこない方もいるかもしれません。具体的な活用例は以下を参考にしてください。
メルマガ・ニュースレターの活用例
| 新商品・サービスの告知 | 新しい商品やサービスをいち早く知らせることで、購入意欲を喚起します。 |
| キャンペーン情報の配信 | 限定セールや特典付きキャンペーンを告知して、購買行動を促進させます。 |
| お役立ち情報の共有 | ユーザーの課題解決に役立つ情報を提供することで、信頼を獲得できます。 |
効果的なメルマガ・ニュースレターのポイント
メルマガやニュースレターは、見込み顧客から既存顧客まで、幅広い層に対して効果的な情報発信が可能なコンテンツ形式です。戦略的に配信内容を設計することで、顧客との関係を深め、成果につなげられます。
| 魅力的な件名の設定 | 開封率を高めるため、短く分かりやすい件名を設定します。具体的なメリットや緊急性を示す言葉を入れると効果的です。 |
| 読みやすいデザイン | スマートフォンでも見やすいレイアウトや、視認性の高いデザインを採用します。 |
| 価値ある情報提供 | 単なる宣伝ではなく、ユーザーにとって有益な情報を盛り込むことで、購読継続率を向上させます。 |
プレスリリース
プレスリリースは、新商品やサービス、イベント、企業の取り組みなどの情報を報道機関やメディアに向けて発表するための公式なコンテンツに位置されます。
新聞、雑誌、テレビ、インターネットメディアといった信頼性の高い媒体に掲載されることで、企業の認知度を向上させるだけでなく、ブランドイメージの向上にも大きな効果が期待できるでしょう。
また、プレスリリース自体が拡散されたり、興味を持ったメディアから取材が来たりすることもあります。結果的に、有料広告などよりも費用を抑えて自社の商品・サービスを宣伝できる点が特徴的です。
プレスリリースの活用例
| 新商品・サービスの発表 | 例: 新機能を搭載した製品リリースや革新的なサービスの導入。 |
| イベントやキャンペーン告知 | 例: 企業セミナーや期間限定プロモーションの案内。 |
| CSR活動や社会貢献の取り組み | 例: 環境保全プロジェクトや地域支援活動の発表。 |
効果的なプレスリリース作成のポイント
プレスリリースは、企業が自社の情報を広く発信し、多くの人々に届けるための強力な手段です。戦略的に活用することで、メディアやユーザーとの接点を増やし、ビジネスチャンスを生み出す可能性が広がります。
| ニュース性を意識 | 発表内容が「今、なぜ重要か」を明確にし、読者にとって価値ある情報を提供することが重要です。 |
| ビジュアル的な要素 | 写真や動画、インフォグラフィックを活用することで、情報の伝達力が高まり、メディアに取り上げられる可能性が増します。 |
| 配信タイミング | タイムリーな情報を適切なタイミングで配信することで、ニュース性を高め、メディアからの注目を集めやすくなります。 |
ホワイトペーパー
ホワイトペーパーとは、企業が提供する商品やサービス、業界知識に関する詳細な情報をまとめた公式な資料です。一般的にPDF形式で提供され、ユーザーがメールアドレスや名前などの情報を登録することでダウンロードできる仕組みになっています。
特にBtoBマーケティングにおいて、見込み顧客を獲得するための重要なコンテンツとして活用されています。
BtoBでは意思決定に複数のステークホルダーが関与し、プロセスが長期化することが一般的です。そのため、ホワイトペーパーは、製品やサービスの詳細な情報を分かりやすくまとめ、導入を検討する担当者が社内で共有しやすい形で提供されます。
ホワイトペーパーの活用例
| 商品やサービスの導入ガイド | 商品の特徴や導入の手順、具体的な活用方法を解説した資料。 |
| 業界レポートや調査結果 | 市場動向や業界課題を分析し、ソリューションを提示する内容。 |
| 課題解決のためのハウツー | 特定の業務課題に対する解決策やノウハウを紹介。 |
ホワイトペーパーの制作ポイント
ホワイトペーパーは、単なる資料作成ではなく、見込み顧客の関心を引き付け、購買プロセスを進めるための戦略的なコンテンツです。企業の専門知識や業界洞察を効果的に伝えることで、成果を最大化できるでしょう。
| ターゲットのニーズに応える | ユーザーの課題や興味に直結したテーマを選び、具体的かつ実用的な内容を盛り込みます。 |
| 視覚的に分かりやすい構成 | 図表や写真、箇条書きなどを活用して、視覚的にも理解しやすいデザインを採用します。 |
| 信頼感のあるデザイン | 公式な資料としての体裁を整え、企業の信頼性を高めるレイアウトやフォントを使用します。 |
| 具体的な事例やデータの活用 | 実際の導入事例や統計データを盛り込むことで、説得力を向上させます。 |
ランディングページ(LP)
ランディングページは、商品やサービスの魅力をユーザーに分かりやすく伝え、問い合わせや購入など具体的な行動を促すために設計されたWebページです。特徴は、1ページ完結型のデザインと構成で、クロージング(商品の購入、サービスの契約など)をその場で行える点にあります。
商品やサービスの特長やメリットを、視覚的に魅力的で分かりやすい方法で紹介します。画像、動画、ユーザーの声、具体的な事例を組み合わせることで、ユーザーの興味を引きつけます。
特定の目標達成に特化したWebコンテンツとして、企業のマーケティング活動において大きな役割を果たします。効果的なページを作成し、改善を重ねることで、ユーザー行動を確実に促し、ビジネス成果を最大化することができるでしょう。
ランディングページの構成例
| 1.キャッチコピー | ユーザーの関心を引きつける、簡潔かつ魅力的なメッセージ。 |
| 2.商品の説明 | 商品やサービスの特長、メリット、差別化ポイントを具体的に解説。 |
| 3.視覚的要素 | 写真や動画を用いて情報を分かりやすく伝える。 |
| 4.顧客の声や実績 | 信頼性を高めるためのお客様の声や導入事例。 |
| 5.行動を促すCTAボタン | 「今すぐ購入」「無料で資料請求」などの行動を明確に指示。 |
ランディングページ作成時のポイント
ランディングページは、特定の目標達成に特化したWebコンテンツとして、企業のマーケティング活動において大きな役割を果たします。効果的なページを作成し、改善を重ねることで、ユーザー行動を確実に促し、ビジネス成果を最大化することができます。
| ユーザー目線での構成 | 適切な順序で提示し、疑問や不安を解消する内容を盛り込む。 |
| 視認性の高いデザイン | シンプルで直感的なデザインを採用し、情報の伝わりやすさを重視。 |
| A/Bテストの活用 | 異なるデザインや文言を比較して、効果が高い方を採用する。 |
セミナー・説明会
セミナーや説明会は、ユーザーとリアルタイムで交流しながら情報を提供できる効果的なコンテンツです。商品やサービスに関する説明や、自社の専門的なノウハウを直接伝える場として活用されます。
最大の魅力は、双方向のコミュニケーションを通じて参加者との信頼関係を築ける点です。
また、参加者の反応を直接みられるため、顧客の関心度合いやロイヤリティの高さを把握でき、マーケティング施策の改善に活用できます。
セミナー・説明会の代表例
| 商品・サービスの紹介 | 新商品や新サービスの詳細を解説し、その利便性や価値をユーザーに直接伝えます。 |
| 業界ノウハウの共有 | 専門的な知識や業界動向について解説することで、企業の専門性をアピールします。 |
| ユーザー教育 | 商品・サービスの効果的な活用方法や導入事例を説明し、ユーザーの理解を深める場として活用します。 |
効果的なセミナー・説明会のポイント
セミナーや説明会は、単なる情報提供の場ではなく、参加者との接点を深め、企業の価値を直接的に伝える機会です。以下のポイントを意識して有益な企業のコンテンツにしましょう。
| 明確なテーマ設定 | 参加者が興味を持つテーマを設定し、具体的で分かりやすい内容を準備します。 |
| 参加者とのコミュニケーション | 質疑応答やディスカッションの時間を設け、参加者の興味関心を促進します。 |
| 資料などコンテンツの充実 | 視覚的に分かりやすいスライドやデモンストレーションを準備し、内容をより魅力的に伝える工夫をします。 |
| セミナー後のフォロー | セミナー後に参加者へフォローアップメールを送付したり、関連資料を提供することで、関心を維持し、次のステップへつなげます。 |
コンテンツ制作のメリット
コンテンツ制作には、企業が得られるさまざまなメリットがあります。ここではコンテンツ制作を行うメリットを、大きく3つに分けて解説します。
集客効果を期待できる
自社コンテンツを制作すると、自社を知らなかった層に興味を持ってもらうきっかけが作れます。さらに、ユーザーのニーズを満たし続けられれば、長期的な集客効果が期待できます。
定期的にユーザーに寄り添ったコンテンツを発信し続ければ、集客したユーザーはリピーターになってくれる可能性があります。
一度呼び込んだユーザーが競合に奪われないようにするには、ユーザーとの信頼関係の構築が重要です。「このジャンルの問題解決に関する情報を得るには、このコンテンツを見れば良い」とユーザーに思わせるようなコンテンツ制作を心掛けましょう。
ブランディングを行える
コンテンツ制作は、企業のブランディングにも有効です。制作したコンテンツから企業の取り組みを知ってもらい、企業のイメージをユーザーに印象付けられます。制作したコンテンツを、そのまま企業の顔として活用可能です。
さらに、企業ブランドが確立すると新たな宣伝・広告をせずとも商品が売れやすくなるため、コスト削減にもつながります。
自社の永続的な資産となる
自社コンテンツは、自社の永続的な資産になり得ます。広告などの発信は、潜在顧客を創出したり注目を集めたりするための重要なマーケティング方法のひとつですが、得られる効果は一時的です。
一方コンテンツ制作は、記事や動画などのコンテンツを永続的に持ち続けられる上にノウハウが蓄積され、永続的な資産となります。
コンテンツ制作を行うデメリット
コンテンツ制作にはメリットだけではなく、事前に注意すべきデメリットもあります。ここではコンテンツ制作のデメリットを、大きく2つにわけて解説します。
成果が出るまで時間がかかる
コンテンツは、広告と比べると制作・公開してから成果が出るまで時間がかかる傾向にあります。コンテンツを公開しても、多くのユーザーの目に入るようになるまで効果が出ないためです。
例えば、オウンドメディアの場合、公開から半年程度は検索画面に上位表示されないこともあります。ユーザーにとって有用なコンテンツが蓄積し、価値あるサイトだと検索エンジンから評価されるまでに、時間を要するからです。
そのため、即効性のある広告など、ほかの手法とも組み合わせながら、中長期的な視点でマーケティング施策の計画を立てる必要があります。
リソースの確保が難しい場合がある
コンテンツ制作には、一定の作業時間や十分な人材が必要であり、自社のリソースが限られていると対応が難しい場合があります。特に、質の高いコンテンツを制作するには、企画やデザイン、サイトの運用などの専門的な知識をもつ人材の育成・確保が不可欠です。
また、コンテンツマーケティングではコンテンツを継続的に追加したり、発信した内容が古くならないよう、定期的に見直したりする必要があります。
しかし、コンテンツの量が増えると制作や修正にかかる工数が増え、管理が煩雑になりかねません。コンテンツの管理が疎かになると質の低下を招き、信頼低下につながる可能性も考えられます。
自社内でのリソースの確保が難しい場合には、外注する方法もあります。ただし、その分コストがかかる点には注意が必要です。
コンテンツ制作に必要な5つのスキル
コンテンツ制作は、単なる情報発信ではなく、ターゲットの心を動かし、具体的な行動を促すための重要なマーケティング手法です。質の高いコンテンツを制作するためには、以下のようなスキルが必要とされます。
スキル1.企画能力
スキル2.ディレクション能力
スキル3.進行管理能力
スキル4.コミュニケーション能力
スキル5.リサーチ能力
企画能力
質の良いコンテンツを制作するために欠かせないのが、ターゲット層の本質的な悩みを解決する企画です。例えば、SEO記事を作る場合を想定しましょう。
キーワード選定のみ行い、企画やライティングは社外のライターに任せることもできますが、想定したとおりの内容で制作されるとは限りません。ディレクターが中心となって、ターゲット層に適した企画を立てましょう。
コンテンツ制作会社の未知株式会社の企画作成では、見込み客のペルソナを作成するところから始めます。ペルソナを基準としたカスタマージャーニーを1記事ごとに作成し、検索ボリュームなども考慮してテーマを決定しています。実際にクライアントに提出している企画の枠を添付します。ぜひ参考にしてください。
クエリに応じて、評価されるページは異なるため、企画ではペルソナとの親和性だけではなく、どのようなテーマであれば上位を狙えるのか見極める力も不可欠です。
企画力といっても、必ずしもディレクターひとりでアイデア出しを行う必要はありません。周囲からアイデアを募り、最終的にディレクターがまとめる方法でも良いでしょう。
普段の何気ない雑談からヒントを得る場合もあるため、常にアンテナを張り、気になる言葉やアイデアのメモを取っておくと役立ちます。一度まとまったアイデアを再度ブラッシュアップすると、より良い企画に仕上がります。
ディレクション能力
ディレクターとして、チームをまとめる力も欠かせません。コンテンツ制作において求められるディレクション力は、クライアントや自社の企業イメージやブランドを守りつつ質の良いコンテンツ制作ができるスキルです。
ディレクション力を発揮させるためには、下記の点を意識して現場の陣頭指揮をとることが重要です。
・明確なビジョンをもつ
・曖昧なまま進行しない
・段取り・役割を把握しておく
・入念に準備しておく
コンテンツ制作を進める前に、どのような目的でどのような効果を狙うのか、ビジョンを明確にしましょう。仕上がりイメージも可能な限り明確に描いておくことで、スタッフやライターの手配時も、企画と人選のミスマッチが起こりにくくなります。
ビジョンが明確でない場合は「お任せします」と抽象的な指示をしてしまい、想定とは異なるコンテンツに仕上がるリスクもあります。
制作進行中も、曖昧なまま次のステップへ進まないことが重要です。たとえばキーワードやデザインなど選択を迫られる場面では、漠然としたイメージでどちらか一方を選ぶのではなく、最初に明確化したビジョンに沿って高い効果が期待できるほうを選びましょう。
複数名が案件に関わる場合、コンテンツ制作の段取りを把握することと、各スタッフやライターなど外注先の役割を分担することもディレクターの仕事です。撮影やインタビューを行うのであれば、事前準備も入念に行わなくてはなりません。
進行管理能力
ディレクション力の中にも含まれますが、進行管理能力も重要なスキルです。コンテンツ制作の現場では、下記のポイントを意識した進行管理が求められます。
・余裕のあるスケジュール管理をする
・スケジュールはメンバー全員で共有する
・レスポンスは早めに済ませる
・スタッフの管理・サポートを行う
・お金の管理を徹底する
スケジュールは締め切りから逆算して考え、更にトラブルのリスクも考慮したうえで余裕のある日数を設定します。
スケジュール管理で重要なポイントは、一部の人間だけではなくチーム全体で共有することです。スケジュールが曖昧な状態で上司から「なる早でほしい」と作業を割り振られても、担当者はどの程度の優先度なのか判断できません。
また、各スタッフの作業スピードを阻害しないために、連絡や確認に対するレスポンスは早めに済ませることも重要です。意思決定スピードが早いほどその後の作業が早く進むうえ、関係者同士の信頼を築き上げていきます。
進行管理業務の中には、スタッフやお金の管理も含まれています。
スタッフがトラブルに巻き込まれることなくスケジュールどおりに作業できるようサポートしたり、外注ライターやデザイナーが安心して作業できるよう支払時期を明確にしたりと、関係者の管理やサポートもディレクターが行うべき仕事です。
単純にプロジェクトがスケジュールどおりに進んでいるか進捗を確認するだけではなく、スムーズに進められるよう、積極的にチームを支えましょう。
コミュニケーション能力
コンテンツ制作は、ライターやデザイナー、マーケティング担当者など、多くの関係者と連携して行うことが多い作業です。チーム内外で円滑にコミュニケーションを図り、意図を正確に伝える能力が制作プロセスの効率化につながります。
リサーチ能力
良いコンテンツを作成するためには、リサーチ力も必要です。
ライターは指定されたキーワードやテーマに沿って、ユーザーにとって価値のある記事を書くことが求められます。商品知識などクライアントや上司から必要な情報を提供される場合もある一方で、ときには自力で情報収集することもあります。
現在はインターネットの普及により、情報を得ること自体は容易です。しかし、必ずしも入手した情報が正確なものであったり、最新のデータであったりするとは限りません。
ユーザーに正確かつ最新のコンテンツを提供するために、集めた情報の中から、価値のあるものを取捨選択していくリサーチ力が必要です。
【7ステップ】コンテンツ制作の流れ
コンテンツ制作は、複数の作業から成り立っています。今回は、オウンドメディア運用を例に出して、コンテンツ制作の流れを7つのステップを紹介します。
ステップ1.見込み客のペルソナを明確にする
ステップ2.カスタマージャーニーを作成する
ステップ3.見込み顧客のアプローチ方法を思案する
ステップ4.コンテンツのテーマを決定する
ステップ5.コンテンツの構成を作成する
ステップ6.構成に沿って執筆する
ステップ7.執筆したコンテンツを編集する
1.自社の見込み客のペルソナを決める
まずオウンドメディアで集客したい対象を明確にします。どのような見込み客の流入を狙うのか決めておくと、コンテンツ内容にズレが生じにくくなります。
見込み客は性別や年齢など大まかな層で分けるのではなく、ペルソナの作成がおすすめです。年齢や性別はもちろん、どの程度の規模の企業でどのような立場にいるのか、売りたい商品・サービスをプロモートするうえで必要な要素を可能な限り詳しく設定します。
たとえば衣料品を取り扱う場合、プレミアムなラインとスタンダードなラインでは想定される見込み客の年収や社会的地位は大きく異なります。
ターゲットがコンテンツを読んで「自分向けに書かれている」と感じるように、必要に応じて生活習慣や抱えている悩みも設定することがポイントです。
もちろん、やみくもにペルソナを設定しても適切なものにはなりません。ユーザーアンケートの結果や購買状況、SNSの情報などを参考に、リアリティが出るよう肉付けしていきましょう。
2.商品購入までのカスタマージャーニーを作成する
ペルソナの設定は、カスタマージャーニーを作成するうえでも役立ちます。
先に作成したペルソナをもとに、ユーザーが実際にどのような段階を踏んで購入や資料請求、問い合わせなどにステップアップしていくのか、カスタマージャーニーを作成します。
カスタマージャーニーの流れは、下記のとおりです。
・認知
・情報収集
・比較検討
・申し込み(購入)
ユーザーは何らかのきっかけで悩みや課題を認知し、解決するための手段について情報収集します。複数の候補を比較検討したうえで自分に合っていると感じたものを選び、申し込みます。
各ステップにいる見込み客へ、どのようにアプローチしていくか考えましょう。
3.見込み顧客にアプローチできるポイントの割り出し
カスタマージャーニーでどのステップにいるかによって、見込み客に効果的なアプローチ方法は異なります。
ユーザーにとって有益な情報を提供しても、見込み客が適切なステップにいない状態では、コンテンツから購入や資料請求につなげることは困難です。
見込み客を具体的なアクションへ誘導するためには、カスタマージャーニーをもとに、最適なアプローチができるタッチポイントを割り出す必要があります。
例として、各ステップで想定できるタッチポイントは次のとおりです。
・認知:ニュースサイトや業界関連の記事
・情報収集:ウェブサイト、比較・まとめサイト
・比較検討:LP、口コミサイト、関係者のブログ
・申し込み(購入):LP、資料、資料請求後のステップメール
オウンドメディアがニュースや業界関連の記事を発信している場合、認知段階からのアプローチが可能です。
すでに情報収集の段階にいるユーザーへアプローチしたいのであれば、専門的な記事や比較・まとめサイトの作成も効果が期待できます。
たとえば「最近は幼児期からの英語教育が重要」というニュースを目にしたユーザーは、英語教育の必要性を認知します。
次に我が子にどのような英語教育が最適か、情報収集によってさまざまな英語教育の手法やサービスを知るでしょう。更にユーザーは各手法やサービスを比較検討して、最適だと思ったものに申し込みます。
ユーザーが各ステップにいたとき、どのような疑問を抱き、どのような行動をとるか、どのようなアプローチをすると興味関心を引くか、設定したペルソナをもとに想定して、コンテンツ制作に活かしましょう。
4.記事テーマの決定
カスタマージャーニーで整理したペルソナの行動や思考の変化をもとに、ユーザーニーズに合った記事テーマを決定します。
記事を読んだユーザーにどうしてほしいのか(目的)を設定したうえで考えることがテーマ作りのポイントです。商品認知度の向上を目的とするのか、購入や資料請求につなげたいのか考えることで、記事テーマは自然と定まります。
ここで注意したいのが、発信者目線でのコンテンツ制作にならないことです。「ユーザーはこう思うはずだ」「次の行動はこうなるはずだ」と決めつけず、実際のユーザー動向を参考に記事テーマを決めましょう。
ユーザー動向が既存のコンテンツ内容とマッチしていない場合は、方向性を変えてみるのもひとつの解決方法です。事例記事が多い場合は、ノウハウ記事を増やしてみたり比較コンテンツを新たに制作したりすると、マンネリ化防止にもなります。
5.記事の構成案を作成する
記事を執筆するうえで必要不可欠なものが、構成案です。コンテンツ内容がブレないようにするために、記事ごとの構成案を作成する必要があります。
構成案を作成すると、下記のメリットも期待できます。
・記事を作っていく中で、内容がブレない
・ターゲットやコンセプトが明確になる
・既存記事と内容が被らない
構成案のない状態で記事を執筆すると、重要なキーワードを見出しや本文に入れ忘れる恐れがあります。
見出しごとにターゲットやコンセプトがブレてしまうこともあるため、構成案であらかじめ記事の方向性を明確にしておかなくてはなりません。
また、あらかじめ構成案で記事に含めるべき情報を整理しておくことで、既存記事と内容が被ってしまうトラブルも防げます。
基本的な構成は、「タイトル」「リード文」「見出し1」「見出し1-1」「見出し2」「まとめ」です。見出しの数は、記事内容や文字数に応じて増やせます。ひとつの見出しにひとつの内容を書くように意識して構成案を作成しましょう。
たとえば商品のメリット・デメリットを紹介する場合は、メリットとデメリットで見出しを分けると読みやすくなり、記事の質が向上します。
6.ライターもしくは社員で執筆
構成案をもとに、記事を執筆します。
自社にライターやライティング担当の社員が在籍している場合は社内で対応し、外注する場合はライターへ依頼しましょう。
記事執筆とペルソナや構成案の作成者が異なる場合は、入念に打ち合わせておくことが重要です。あらかじめターゲット層や記事の目的を理解したうえで執筆してもらわなくては、想定とは異なる内容で納品されるおそれがあります。
7.作成した記事の編集・校正
完成した記事は、編集・校正を行ってからコンテンツに反映させます。
インターネット上で誰もが手軽に情報を発信・入手できる現在は、コンテンツの信頼性が揺らぎやすい弱点ももっています。
検索エンジンから、ユーザーにとって利便性の高いウェブサイトであると評価されるためには、記事の編集・校正で少しでも信頼性を向上させることが重要です。記事の編集は見やすさと読みやすさを考慮して行います。話の流れに不自然さを感じる部分があれば、見出しの順番を入れかえることも珍しくありません。
校正では、主に次のポイントが確認されます。
・情報は正確で最新の内容になっているか
・漢字やひらがな、送り仮名など表記ゆれはないか
・不自然な内容・断定的な表現になっていないか
ウェブサイトでもっとも重視されるポイントは、情報の正確さです。構成案に従った内容であることはもちろん、提示されている情報やデータに誤りがないか確認したうえで公開します。
統計など数値を表記する場合は、古すぎるデータは現代の状況と異なる可能性があるため、可能な限り新しい情報を反映させる必要があります。
加えて、表記ゆれや、不自然な内容・決めつけにも十分注意しましょう。
コンテンツ制作は社内・社外どっちが良いの?
コンテンツ制作は、内製化することも不可能ではありません。一方で、多少のコストをかけてでも社外に対応を任せたほうが良い場合もあります。
自社はコンテンツ制作を社内・社外どちらで対応するべきか悩んでいる方へ、ここではコンテンツ制作会社に依頼すべきパターンと内製化するべきパターンを紹介します。
コンテンツ制作会社に依頼・外注が良いパターン
コンテンツ制作を社外に依頼する場合、記事執筆のみ依頼する方法もあれば、コンテンツ制作から分析まで一貫して任せる方法もあります。
ここでは完全に外注することを想定して、コンテンツ制作会社に施策をまるごと依頼・外注するべきパターンとして、次の2つをあげます。
■社内でコンテンツ制作チームを編成できない
コンテンツ制作チームを社内に設けられない場合は、施策をまるごと専門会社へ依頼したほうが良いでしょう。中には一部のパソコンが得意な社員に施策を任せる企業もありますが、コンテンツの質を維持することを考えると適切とは言えません。
専門ではない社員に通常業務の片手間で作業を任せても、SEOを考慮したコンテンツ制作は困難です。コンテンツ制作に力を入れれば通常業務を圧迫することとなり、施策が中途半端になるおそれもあります。
本格的にコンテンツ制作へ取り組む場合は専門のチームを編成するべきですが、コストを考えると容易ではないでしょう。オウンドメディア運営は長期的な施策となるため、相応の人件費がかかります。
人件費の長期的な発生を前提とした場合、社内でコンテンツ制作チームを編成することは困難と感じるのであれば、コンテンツ制作会社への依頼を検討してはいかがでしょうか。
プランによっては、新たに人件費をかけるよりも安くプロに施策を任せられるため、高い費用対効果が期待できます。
■迅速に良質なコンテンツをウェブサイトに蓄積したい
短期間で質の良いコンテンツを増やしたい場合も、コンテンツ制作会社への外注がおすすめです。
オウンドメディアは、ある程度のストック記事がなければ検索エンジンによる評価が向上しにくい傾向があります。ウェブサイトの土台となる記事を早く増やしたいのであれば、自社でチーム編成から始めるよりも、コンテンツ制作会社に依頼したほうが効果的です。
実績の多いコンテンツ制作会社なら、質の良い記事や効果的なキーワード選定が期待できる点も大きなメリットです。
自社で経験や知識の少ない社員が試行錯誤しながらコンテンツ制作を行うと、慣れるまで時間を要するでしょう。質の低い記事を増やすと、ユーザーや検索エンジンからの評価も下がってしまいます。
効果的な施策やキーワード選定を知り尽くしているプロに最初から任せれば、質の低い記事を量産して検索エンジンからの評価を下げる心配もありません。
コンテンツ制作会社に依頼・外注しないパターン
ある程度のコストをかければ、コンテンツ制作会社に依頼したほうが効率的にオウンドメディアを運営でき、集客につなげられます。
一方で、完全に外注することで将来的にデメリットが生じるおそれもあるため、社外に施策を依頼するかどうかは慎重に検討しなくてはなりません。
前述のメリットがありつつも、コンテンツ制作会社への依頼・外注は避けたほうが良いパターンとして、次の2つがあげられます。
■メディアのブランディングが確立している場合
オウンドメディアを1から作るのではなく、すでにある程度の運営歴がある場合は、安易に他社へ運営を任せないほうが良いでしょう。
メディアとしてのブランディングが確立しているのであれば、これまでの運営方法を継続したほうがメリットにつながります。
下手に運営体制を変更すると、下記のデメリットが生じかねません。
・メディアの雰囲気が変わってしまう
・既存ユーザーに合わないコンテンツが増えてしまう
すでにブランドが確立されたメディアの運営を、新たにコンテンツ制作会社へ任せてしまうと、雰囲気が変化してしまうおそれがあります。
課題を抱えているメディアが改善のために他社の力を借りるのであれば、良い変化がもたらされることが期待できますが、すでにファンを獲得しているメディアの場合は必ずしも良い結果になるとは限りません。
既存ユーザーに合わないコンテンツが増えれば、「安っぽくなった」「運営がそっけなくなった」とマイナスイメージにつながるでしょう。
新たなファンを取り込むつもりが、既存ユーザーを減少させる結果となることもあります。
リスクを考慮したうえで外注に切り替える場合は、確立されたブランドやメディアの雰囲気を重視してくれるコンテンツ制作会社を選ぶことが重要です。企業理念や文化、ブランドイメージの共有も含めて入念なイメージのすり合わせが欠かせません。
■社内にノウハウを蓄積したい場合
社内にコンテンツ制作やSEOのノウハウを蓄積したい場合も、外注は慎重に検討したほうが良いです。
自社のリソースを割かずに済むことや、ノウハウのない企業でも効率的にコンテンツ制作ができるメリットがある外注は、一方で自社の社員がまったく専門知識や技術を学べないデメリットもあります。
ノウハウを蓄積したい場合は、時間を要することを前提に社内でコンテンツ制作チームを編成することも検討してはいかがでしょうか。あるいは、完全にコンテンツ制作を外注するのではなく、社員も施策を学べる機会を設ける外注の仕方もおすすめです。
未知株式会社では、コンテンツ制作を丸投げして終わるのではなく、契約満了後は自社でコンテンツ制作ができるよう、内製化のサポートも行っております。未知株式会社で提供するコンテンツ制作の内製化サポートは、主に2つのパターンがあげられます。
コンテンツ制作を進行していると、コンテンツ制作全体の流れを自然と学ぶことができます。
カスタマージャーニー作成やテーマ決定、企画作成、ライティングなどの制作方法や、ディレクションや業務について、関わりながら学ぶことで、理解度を高められる方法です。
進行に関わることで漠然と学ぶのではなく、より具体的に内製化コンサルを受ける方法です。
企業様に作成いただいた企画案や記事を弊社がチェックして、SEOやコンテンツマーケティングの観点からアドバイスします。また、キーワード戦略のみ弊社が担うことも可能です。
このように「自社にノウハウを残したいが、最初から完全に内製化するのは不安がある」という場合は、内製化サポートのあるコンテンツ制作会社への外注をおすすめします。
コンテンツ制作会社を選ぶ際のポイント
コンテンツ制作会社と一口に言っても、対応しているサービスや料金システムは異なります。
費用面のみを重視すると求めているサービスが含まれていなかったり、コンテンツの仕上がりに納得できなかったりとトラブルが発生するおそれがあるため、外注先は慎重に決めなくてはなりません。
ここからは、コンテンツ制作会社を選ぶうえで重視したい、ポイントを紹介します。
運営支援まで行ってくれる会社か
オウンドメディアはユーザーに有益な情報を提供するだけでは、想定したような効果を得られません。
最終的に自社の利益へつなげるためには、狙ったターゲットに流入してもらえるような施策や、ユーザー動向に合わせた導線の改善など、コンテンツ制作後の運営が重要です。
コンテンツ制作会社を選ぶときは、運営支援も含めて総合的に頼れるところを選びましょう。
トレンド調査やユーザーニーズにマッチした記事の提案から、コンテンツ公開度の分析、改善策の提案まで一貫して頼れる会社なら、企業イメージとオウンドメディアにズレが生じる心配もありません。
ただし、記事執筆のみやデザイン込みのコンテンツ制作のみを依頼する場合よりも、費用は高くなる点に注意してください。
どこまで対応してくれるのか、費用対効果を意識しつつ必要な運営支援が揃っているコンテンツ制作会社を選ぶことがポイントです。
自社が抱えている課題に近い成功事例を持っているか
オウンドメディアに関して各企業が抱えている課題は、それぞれ異なります。たとえばライティング面に課題を抱えている場合もあれば、デザインやウェブサイト構成で困っている企業もあります。
コンテンツ制作会社を選ぶときは、実績の多さだけではなく、自社が抱えている課題に近い成功事例が多いかどうかを重視しましょう。
記事の執筆ひとつとっても、狙うターゲットが異なれば求められるライターやコンテンツ制作会社も異なるものです。BtoBを主とする企業が、業界向けの記事を増やしたい場合は、専門的なライティングができるコンテンツ制作会社を探すなど、実績のこまかな内容も含めて選ぶことが大切です。
コンテンツ制作を外注する場合の費用相場
コンテンツ制作を外注する場合の費用は、制作を依頼する対応範囲により異なるため、事前に外注先へ確認しましょう。目安として以下が費用相場です。
|
費用相場 |
対応範囲 |
|
~10万円 |
・記事制作程度 |
|
10万~30万円 |
・ページの増設 |
|
30万~50万円 |
・取材記事制作 |
|
50万円~ |
・オウンドメディアのアップデート |
制作費が高くなるのは、大規模な制作が必要になる新規事業の立ち上げが伴うような場合です。また、SEO施策も取り込んだ設計にしたいなどの要望が加わる場合も、費用が上がる傾向にあります。
まとめ
現代のマーケティングにおいて、コンテンツ制作は単なる作業ではなく、戦略的な取り組みとして捉えるべきです。目的やターゲットに合わせたコンテンツを計画的に制作し、ユーザーとのつながりを深めながら、長期的な成果を目指していきましょう。適切なスキルとアイデアを活用することで、コンテンツ制作は企業の成長を支える強力な武器となるはずです。