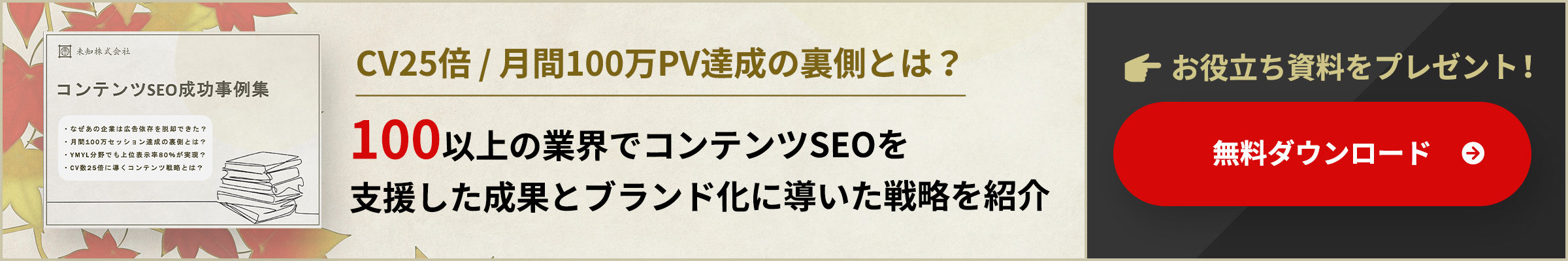目次
コンテンツSEOとは
コンテンツSEOとは、オウンドメディアなどのWebサイトにユーザーの検索意図を満たした良質なコンテンツを掲載して、自然検索からの流入を獲得するSEO手法のことです。
検索ユーザーにとって有益なコンテンツを継続的に提供することで、GoogleやYahoo!などの検索エンジンから高く評価され、検索順位の上位化が見込めます。
また、コンテンツマーケティングと意味が混同する方もいますが、別物と捉えましょう。コンテンツマーケティングは、記事やメルマガなどのコンテンツを用いて、見込み顧客を集客し、消費行動を促すマーケティングのことです。
一方のコンテツSEOは、コンテンツマーケティングの手法のひとつになります。検索エンジンを通して、ユーザーに価値あるコンテンツを提供して、自社のWebサイトに集客します。
コンテンツSEOを始める前に知りたい、Googleの変遷
現在、検索エンジンで上位表示を狙うためには、コンテンツSEOが欠かせません。多くの企業がコンテンツSEOに注力する理由は、Googleのアルゴリズムのアップデート変遷にあります。
コンテンツSEOを本格的に始める前に、まずはコンテンツSEOが重視される要因となったGoogleの変遷について理解しておきましょう。
ブラックハットSEOの拡大・終息
SEOのさまざまな手法は、ブラックハットあるいはホワイトハットと呼ばれる2タイプに分類されます。2012年ごろに、各検索エンジンがユーザーの利便性を重視する方向へ舵を切るまでは、手軽に上位表示を狙えるブラックハットSEOが台頭していました。
ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの特徴は、次のとおりです。
・ブラックハットSEO:被リンク施策などアルゴリズムをハックするSEO
・ホワイトハットSEO:アルゴリズムのハックを狙わないSEO
ブラックハットSEOは、検索エンジンのアルゴリズムの穴を突くような手法で無理やり上位表示させる手法です。たとえば不自然にキーワードが散りばめられた記事や、他サイトの文章を貼り付けた記事、被リンクの大量設置などがあげられます。
これらのブラックハットSEOが悪質と呼ばれる理由は、検索エンジンで上位表示されているにもかかわらず、低品質なWebサイトが多いことです。ブラックハットSEOの影響により、ホワイトハットSEOのコンテンツが上位表示されにくくなる状況が続きました。
ユーザーから見ると利便性の低いWebサイトが上位表示されやすくなった状況は、検索エンジン運営者のGoogleにとっても頭の痛い問題です。
そこで、ユーザーの利便性を著しく阻害するブラックハットSEOへの対処として、検索エンジンのアルゴリズムに対し、次のアップデートが行われることとなりました。
・ペンギンアップデート
・パンダアップデート
それぞれを詳しく解説します。
■ペンギンアップデート
ペンギンアップデートとは、主にリンクの質に対する評価を見直した施策です。ブラックハットSEOのひとつ『リンクの大量設置』を見抜く精度が上がりました。2012年4月に初めて実施されてから、数回アップデートが行われました。
ペンギンアップデートがリンクの質を判断するポイントは、低品質なWebサイトからのリンクです。リンク集や他サイトのコピーコンテンツなど、ユーザーにとって利便性の低いWebサイトからのリンクが多い場合、検索エンジンで上位表示されにくくなります。
SEO目的で相互リンクを貼っていたり、低評価のディレクトリ登録サイトを利用していたりと、ブラックハットSEOで利用されやすいリンク手法を見抜きます。
2016年9月には、ペンギンアップデートも、継続的に更新されるコアランキングアルゴリズムに組み込まれました。従来は手動で行われてきたペンギンアップデートが、現在はオートマチックかつ継続的に行われています。
■パンダアップデート
パンダアップデートは、低品質なコンテンツほど順位が下がりやすく、良質なコンテンツが上位表示されやすくなる施策です。
日本で初めてパンダアップデートが行われたのは、2012年7月でした。同年4月のペンギンアップデートに加えて、パンダアップデートが追い打ちをかけたことで、悪質・低品質なコンテンツは急激に検索結果の順位を下げることとなりました。
パンダアップデートがコンテンツの質を評価するポイントは、複数あげられます。たとえば専門性の高い記事は、専門家による執筆や監修が行われているものほど評価されやすく、興味深い情報や分析・根拠を掲載しているものも上位表示されやすくなります。
一方で低品質とされやすい記事の特徴は、他サイトの文章を貼り付けただけのコピーコンテンツや、広告が本文の閲覧を著しく妨げるものなどです。
パンダアップデートもペンギンアップデートと同じく、2013年3月ごろからコアランキングアルゴリズムに組み込まれています。
低品質コンテンツによる、コンテンツスパムの拡大
被リンク施策をメインとしたブラックハットSEOの効果が弱まったことにより、Webサイトにコンテンツを大量追加する方法がSEOの本流となりました。
この時のGoogleはまだコンテンツの理解度が低く、1記事内の文字数や網羅性のみで評価を下していました。
結果、コンテンツスパムの拡大により、医療・健康系サイトでも信頼性の低いコンテンツが上位表示されるようになりました。
医療・健康系のコンテンツは、アフィリエイトサイトやECサイトでも多く作成されています。中には、低品質かつ信頼性の低い記事を大量に有するまとめサイトもあり、社会問題となりました。
誤った情報でトラブルに発展するリスクを軽減するために行われたのが、健康アップデートです。
■健康アップデート
健康アップデートとは、その名のとおり医療・健康系のコンテンツを主な対象とした施策です。医療従事者、専門家、医療機関など、提供元の信頼性が高く、有益なコンテンツが上位表示されるようになります。
結果、低品質なものや、専門家以外が作成した信頼性の低いコンテンツに加えて、まとめサイトやQ&Aサイトも順位を大きく下げることとなりました。
Googleの精度向上による、コンテンツSEOの浸透
ペンギンアップデートやパンダアップデートに加えて、健康アップデートも行われたことにより、Googleの検索結果は大幅に精度向上を見せました。ユーザー目線では有益かつ信頼できる情報に辿り着きやすくなった一方で、サイト運営者側は小手先のSEOを利用できなくなっています。
Google自体が「量より質」を意識している現在、自社サイトの検索順位を上げるためには、質の良いコンテンツの作成が欠かせません。検索エンジンをハックしようとせず、ユーザーが求める有益な情報を提供することで順位を上げる正攻法のホワイトハットSEOが必要です。
ホワイトハットSEOは、アルゴリズムに沿った方法で検索エンジンから高評価を得ることで上位表示を目指します。必然的に、ユーザーに有益なコンテンツを提供するコンテンツSEOが重視されるようになりました。
コンテンツSEOを行うメリットとリスク
コンテンツSEOに注力する理由は、検索エンジンで上位表示されやすくなるだけではありません。コンテンツそのものの価値を上げていくことにより、さまざまなメリットが得られます。
コンテンツSEOのメリット
コンテンツSEOの施策を取り入れたWebサイト作りは、長期的なメリットを得られます。
・Webサイトの資産性が高くなる
・自社の専門性を伝えられ、信頼感が熟成される
・自社サービスのブランド認知を高めてくれる
・施策をやめても集客効果が持続する
・長期的に考えるとコストパフォーマンスが高い
■メリット1.Webサイトの資産性が高くなる
第1にあげられるメリットが、コンテンツSEOによってWebサイトの資産性も高くなることです。
コンテンツそのものを高品質化させる施策は、Webサイト全体の評価を高めてくれます。質の良いコンテンツが増え続ければ、利便性の高いWebサイトとして多くのページが上位表示されるようになり、ユーザーの流入増加につながるでしょう。
一度投稿したコンテンツは、削除しない限りインターネット上で24時間休むことなく集客に役立ってくれます。上位表示されない場合も追記・リライトを行うことで、順位の上昇が狙えます。
また、Webサイトの資産性は、集客以外の効果にもつながる重要なポイントです。たとえば作成しているWebサイトのうち、一部を事業縮小などで閉鎖することとなった場合、第三者に売却して現金化することもできます。
高品質なコンテンツが多く、アクセス数の多いWebサイトは、買い取りを希望する企業や個人事業主が少なくありません。何もせず閉鎖するだけでは1円にもなりませんが、売却することで資産としてまとまった現金を得られます。
SEO施策にかかる手間を省略できるため、中古サイトはニーズが高く、売却先の選択肢も豊富です。良質なWebサイトほど、集客としても、売却用としても高い資産性が期待できます。
■メリット2:自社の専門性を伝えられ、信頼感が醸成される
例えば、製造業の会社がコンテンツSEOを行う場合、職人ならではの視点でしか伝えられない情報があるといったように、専門性の高い記事を増やせば増やすほど、受注前から信頼性を高められます。
特定の製品について、第三者が解説できるのは、パンフレットに記載されたスペックなど一般的な知識のみです。多くの競合に記載されている情報しかないような、オリジナリティに欠けるコンテンツしか完成しません。
職人の場合、開発にともなうエピソードや工夫したこと、製品の効果を高める使い方など、専門性が高くオリジナリティのある記事を作成できます。
商品やサービスに対して熟知しているからこそ解説できる情報は、他社が容易に真似できない重要な要素です。
競合サイトにない情報を盛り込めば、「このサイトが詳しくて分かりやすい」「この会社は業界を熟知している」と、ユーザーや企業からの信頼を獲得できます。
同じ情報を掲載しているとしても「なぜ、そうなるのか」「どんな仕組みなのか」をより詳しく記載していれば、専門性の高さを伝えられます。
■メリット3.自社サービスのブランド認知を高めてくれる
コンテンツSEOで各ページが検索結果の上位表示を占めることとなれば、自社サイトの権威性や信頼性の向上にもつながります。結果、自社サービスのブランド認知も高めてくれます。
ブランド認知の向上は、集客において欠かせない戦略のひとつです。競合の多い現代は、特定の分野で、いかに第一想起(何かを購入・利用しようとしたとき、真っ先に思い浮かべるブランドのこと)を獲得するかが重要視されています。グローバル企業の多くのブランディングも第一想起を意識した戦略を取り入れています。
コンテンツSEOで上位表示されるキーワードが多くなれば、自社サービスをユーザーの第一想起に位置づけることができます。複数の商品・サービスを検討するときも、第一想起であれば真っ先に候補となるでしょう。
■メリット4.施策をやめても集客効果が持続する
作成したWebサイトや各コンテンツは削除しない限り残るため、永続的な集客効果が期待できます。施策をやめてもコンテンツが残っていれば、検索エンジンからの流入は続き、商品・サービスの購入を促してくれます。
高い集客効果を維持するためには、定期的なコンテンツの分析や改善といった施策が必要です。しかし、施策をやめたところで突然順位が下がったり、流入がゼロになるわけではありません。
アルゴリズムのアップデートによって多少順位が変動することがあっても、コンテンツそのものの有益性が残っていれば、集客効果は持続します。
■メリット5:長期的に考えるとコストパフォーマンスが高い
前述のとおり、施策をやめても瞬時に順位や集客力に影響が出るわけではありません。
ある程度の集客効果が持続するため、有料の広告を繰り返し打ち出すよりも安価にユーザーの流入を促せます。
テレビCMやオンライン広告は、契約期間が終わると放送・表示されなくなるうえ、手法や出稿範囲によっては高コストです。
コンテンツは半永久的に集客してくれることを考えると、長期的なコストパフォーマンスに優れているといえます。
長期的な運営でコンテンツ数が増えれば、ユーザーを流入させる入り口も多くなります。
ビッグワード(検索エンジンで多くのユーザーが検索するキーワードのこと)で検索順位が下がったとしても、コンテンツ数が多ければ、競合の少ないスモールキーワード (検索回数が少ないニッチなキーワードや、いくつかの単語を組み合わせた複合キーワードのこと)で集客可能です。
コンテンツSEOのリスク
コンテンツSEOは、資産性やブランディングなど複数のメリットがある一方でいくつかのリスクもあげられます。
ここでは、コンテンツSEOを本格的に行ううえで、あらかじめ理解しておくべきリスクをお伝えします。
・コンテンツの作成に費用と人手が必要になる
・集客やブランディングへの即効性がない
・コンテンツの内容をメンテナンスする必要がある
■コンテンツの作成に費用と人手が必要になる
コンテンツSEOを行うためには、検索エンジンからユーザーにとって利便性が高いと認められるようなコンテンツを増やす必要があります。質の良いコンテンツを継続的に作成するとなると、相応の費用と人手が欠かせません。
たとえば医療・健康に関する記事や法律関係の記事を作成する場合、資格や知識のないライターが書いたものでは、信頼性に欠けます。検索エンジンから高評価を得るためには、コストをかけて専門家に執筆や監修を依頼するなど、コンテンツの信頼性を高める必要があります。
専門性が厳密に求められない内容であっても、閲覧したユーザーへ価値のある情報を提供するとなると、コンテンツ作成にある程度の費用や人手が必要です。
また、記事をライティングする前に、ユーザーニーズの調査やキーワード選定、トレンド調査などの工数も発生します。場合によっては、取材や写真撮影、動画制作など、より質の高いコンテンツにするための作業も加わるでしょう。
■集客やブランディングへの即効性がない
コンテンツSEOは、短期間で集客やブランディング効果を発揮するものではありません。施策の即効性がない理由は2つあげられます。
1.検索エンジンの評価が安定するまで時間がかかる
Webサイトに追加したコンテンツは、各検索エンジンのクローラーに発見されることで評価され、検索順位が決定します。
Webサイトの情報収集を行う自動巡回プログラムのことです。クローラーが収集してデータベース化(インデックス化)した情報をもとに、検索結果の順位が決定する仕組みです。
クローラーがコンテンツの情報を収集して、検索エンジンがアルゴリズムにもとづいた評価をするまで、ある程度の時間を要します。よって、どんなに信頼性が高い情報を盛り込んだ有益なコンテンツであっても、即座に上位表示されるのは難しいでしょう。
2.コンテンツの数が少ないうちは評価が上がりにくい
流入元が多ければ多いほど、Webサイトの集客力は向上します。高品質なコンテンツを数多く作成し、検索エンジンの上位表示を占めることで、Webサイト全体の評価も高くなります。
コンテンツが少ないうちは上位表示される数量も少なく、集客につながりません。
上記2つの理由により、コンテンツSEOは長期的に取り組むことを前提としています。集客やブランディングに即効性を求める場合、他の施策と組み合わせるなどの工夫が必要です。
■コンテンツの内容をメンテナンスする必要がある
高い集客力を維持したり検索順位を上げたりするためには、コンテンツの継続的なメンテナンスが欠かせません。
Googleの変遷で触れたペンギンアップデートやパンダアップデートのように、突然、大々的なアルゴリズムの精度向上が行われることがあります。さらにペンギンアップデートやパンダアップデートが現在、コアランキングアルゴリズムに組み込まれている点からも分かるように、検索エンジンは進化し続けるものです。
現時点では高評価なコンテンツがアップデートの影響で上位表示されなくなったり、順位が不安定になったりする可能性もあります。上位表示を維持できるよう、コンテンツ側もアルゴリズムに対応した変化が必要です。
コンテンツSEOが成果に結びついた事例
コンテンツSEOの施策次第では、商品やサービスの問い合わせや売上につながるケースもあります。
成果を得るためには、自社の課題を洗い出して的確な施策を行うことが大切です。
ここでは、実際に弊社がコンテンツSEOのご支援をした、クライアント様の成功事例をご紹介します。
【美容・ダイエット関連メディアの事例】
ミス・パリ・グループ様は、女性向けサロン「エステティック ミス・パリ」と男性向けサロン「男のエステ ダンディハウス」の運営企業です。
プロジェクト前はダイエットの手段のひとつに「エステ」という選択肢が一般化されておらず、集客や認知拡大が課題でした。
弊社は、美容やダイエットに関する情報を発信するメディア のコンテンツSEO施策を提案しました。
Googleが掲げるYMYL(Your Money or Your Life/Google検索品質評価ガイドラインで示されている特別な分野のこと)とともに、薬機法にも配慮した記事を継続的に発信。
ユーザー心理に寄り添ったお役立ちコンテンツを提供し続けたことで、施策開始から1年後には広告流入よりも自然流入が増え、ビッグキーワードでも集客できるようになりました。
認知度向上にともない、検索エンジンからの自然流入が増えたことで、広告費の大幅な軽減につながっています。
【求人・人材関連メディアでの事例】
人材派遣企業である株式会社グッド・クルー様は、入社後の育成支援に注力していることが特徴です。入社後の手厚いサポートが好評を得ている一方で、エージェントを介してでなければ集客できない点に課題を感じていらっしゃいました。
弊社が認知拡大の施策としてオウンドメディア制作とコンテンツSEOの継続的な発信です。中途、バイト、新卒のすべてを集客できるメディアに育てることを最終目標に置き、堅実に狭い間口で認知拡大を目指しました。
安定的に集客できるメディアとなるように、3年間の長期計画のもと認知度を徐々に向上させました。結果、1年後には施策開始直後の20倍以上のPV数を実現しています。
施策の中で好評いただいたのが、業界やキャリア形成に関する記事の公平性です。
自社制作の場合は執筆者のバイアスがかかりやすい記事を、弊社が第三者の立場から作成したことで、客観的な内容に仕上がりました。
弊社が実施したより具体的な戦略/戦術を纏めた資料は、以下のバナーからご確認いただけます!
コンテンツSEOを意識した記事の作り方
検索エンジンで上位表示されるコンテンツを増やすためには、ここまで解説してきたポイントを含めつつ、コンテンツSEOを意識して記事を作りましょう。
ここからは、高品質な記事の作り方を紹介します。
インフォメーショナルクエリに属するキーワードをターゲットにする
ユーザーが検索エンジンを利用するときに使用するのが、単語やフレーズ、複数の単語の組み合わせといった検索クエリです。検索クエリは3種類あり、中でもインフォメーショナルクエリを狙うのがコンテンツSEOではおすすめです。
インフォメーショナルクエリとは、情報収集を目的とした検索クエリのことです。ユーザーが人気商品について調べたり、抱えている課題の解決策を探したりと、情報を得るために使用する単語やフレーズなどをさします。
インフォメーショナルクエリを狙う理由は、残りの2種類の検索クエリである「トランザクショナルクエリ」と「ナビゲーショナルクエリ」では、現状のGoogleの仕組み上上位表示が難しいためです。
「トランザクショナルクエリ」は購入や申込みを目的としたキーワードを指します。例えば「家具 通販」などです。
このようなキーワードの場合、大手ECモールや通販サイトが上位表示される傾向が強く、いくらコンテンツを追加しても上位表示の見込みは低いです。
同じように「ナビゲーショナルクエリ」だと判断されたキーワードは、特定の企業や差ービスに関するページが優先的に上位に表示されます。
このような理由から、「トランザクショナルクエリ」と「ナビゲーショナルクエリ」ではなく「インフォメーショナルクエリ」を狙うコンテンツを作成するのがおすすめです。
そのキーワードの検索意図を考え、構成・見出しを作る
インフォメーショナルクエリに属するキーワードの選定で、ある程度ターゲットユーザーが絞り込まれます。どのキーワードについて記事を作成するのか決めたら、次は構成・見出しを作っていきましょう。
ユーザーがなぜ、そのキーワードを入力したのか、検索意図を念頭に構成を練ります。たとえば「結婚式 参列者 服」で調べたユーザーは、どのようなことを知りたいと思っているでしょうか。
・結婚式の参列者の服装のマナーについて知りたい
・結婚式に参列するための服はどこで買うのか知りたい
・結婚式の参列者に人気の服について知りたい
このように、同じインフォメーショナルクエリでもユーザーが求めている情報は多岐に渡るものです。ユーザー目線で、提供する情報や記事に組み込んでいく順番を考えます。
結婚式の服装のマナーを知りたいユーザーを対象とする場合、主とするテーマに加えて、「マナーに沿った服を購入できるお店」の紹介も盛り込めるでしょう。「トレンドのデザインや色」「避けるべきデザインや色の具体例」など、テーマをさらに掘り下げられる見出しを追加することで、コンテンツの有益性が向上します。
記事の導入文は最重要なので、全体作成後に書く
記事の導入文は、ユーザーが最初に読む場所です。本文を読み進めていくかどうか決定するための重要な要素でもあります。
ユーザーを本文へ誘導するために、導入文は以下のポイントを意識して作成しましょう。
・記事を読むメリットが伝わる
・「自分のための記事だ」と共感できる
・信頼性や安心感がある
検索エンジンから流入したユーザーは、自分の抱えている課題解決や情報収集を目的としています。導入文で自分の求める情報があると分かれば、本文を読み進んでくれるでしょう。
自分も経験したことのある悩みが取り上げられているなど、共感をもつような内容が含まれている場合も、本文への興味関心は上がります。ただし、大げさすぎる書き方は避けるべきです。「SEOすべての悩みを解決します」と書かれているよりも、「インフォメーショナルクエリのキーワード選びのコツを教えます」など、具体的な書き方のほうが信頼されます。
導入文は本文の傾向を理解したうえで書くことも、重要なポイントです。そのため本文を書き終えた後に導入文を書くことをおすすめします。
独自性・網羅性を意識して、記事を作成する
Googleが重視している「コンテンツの質」の基準についての解説で触れたとおり、内容のサイトの独自性や価値のある記事を作成しましょう。
さらに競合との差別化をはかるためには、情報の網羅性も重要です。表面的な情報のみを紹介している記事は競合に埋もれやすく、検索エンジンからも利便性が特別高いとは判断されません。
オリジナルのアンケート結果を掲載したり、実際にサービスを利用した体験レポートを掲載したりするなど、独自性と網羅性のある記事作りを意識してください。提示した情報に具体的な数字が含まれる場合、情報元を明記することもユーザーの利便性向上につながります。
必要があれば、他サイトからの引用も積極的に行う
Googleのパンダアップデートによる影響からも分かるとおり、コピーコンテンツなど他者のWebサイトから本文を盗用したWebサイトは低評価の対象です。一方で、ユーザーは多くの信頼できる情報を求めています。
正しい情報を提供するために、場合によっては官公庁の資料など一部文章やデータの引用が必要となることがあります。本文のほとんどが引用やコピーとなれば悪質なコンテンツと判断されますが、必要に応じたデータの引用程度であれば、マイナス要素にはなりません。
正しい情報が網羅されていれば、かえって検索エンジンからの高評価につながります。
これはGoogleが論文執筆の仕組みを検索アルゴリズムの基礎としているためです。
引用元と引用部分が分かるような方法で明記し、ユーザーに信頼できる情報を提供しましょう。
テキストだけでなく、オリジナルの画像や図版も入れる
記事本文に加えて、画像や図版も自社でオリジナルのものを用意すると、コンテンツの独自性・価値が向上します。オリジナルの画像や図版は、記事内容を分かりやすくしてくれるうえ、競合との差別化にも役立ちます。
近年は素材サイトが数多く存在しており、無料・安価でコンテンツのイメージに最適な画像が見つかるため、競合同士が同じ画像を使用するケースも珍しくありません。独自に作成した画像や図版を取り入れることで、視覚的なオリジナリティを演出し、差別化をはかりましょう。
ただし注意点として、検索エンジンのクローラーは画像の意味を正しく把握できないことがあげられます。検索エンジンに画像も認識してもらうためには、代替テキスト(alt属性)の利用がおすすめです。
代替テキスト(alt属性)は、画像の表示までに時間がかかったり、正しく表示できなかったりした場合に表示するテキストのことです。たとえば「福利厚生の社員旅行の写真」と代替テキスト(alt属性)を入力して写真を設置すれば、そこに貼り付けられている画像がどのようなものなのか伝わります。
オリジナルの画像や図版に代替テキスト(alt属性)も設定すれば、クローラーに正しくコンテンツを評価してもらえるうえ、画像検索からの流入も期待できます。
読みたくなるtitleやmeta descriptionタグを設定する
titleやmeta descriptionタグも、検索エンジンから流入するユーザーの印象を大きく左右する要素です。titleとmeta descriptionとは、それぞれ以下のとおりです。
・title:記事のタイトル(32文字以内を意識する)
・meta description:記事の概要(120文字程度を意識する)
titleは、その記事が何について書かれているのかを一言で表すものです。コンテンツ上部に表示される他、検索エンジンの検索結果ではmeta descriptionとともに表示されます。
meta descriptionとは、検索エンジンでコンテンツタイトルの下部に小さく表示される文章です。タイトルよりも長い文章で、どのような内容が書かれた記事なのかユーザーに解説しています。
titleやmeta descriptionは、ユーザーを検索エンジンから誘導するための重要な入口となるため、各コンテンツで作成します。ユーザーが「このWebサイトを見れば、ほしい情報が得られる」と判断できるよう、titleやmeta descriptionは検索意図に沿って作成する必要があります。
ターゲットユーザーを誘導するために、狙ったキーワードを盛り込み、簡潔で分かりやすい内容を意識しましょう。すべての文字が検索エンジンに表示されるわけではないため、上記のとおりtitleは32文字以内、meta descriptionは120文字程度で作成します。途中までの表示となっても良いように、重要なキーワードは前半への配置がおすすめです。
記事完成後も、加筆・リライトを継続的に行う
検索エンジンがコンテンツを評価するためのアルゴリズムは、日々進化を続けています。かつてのペンギンアップデートやパンダアップデートが、現在はコアアルゴリズムに組み込まれたように、アナウンスなく実施されているアップデートもあります。
アルゴリズムのアップデートやユーザーニーズに変化が起これば、上位表示されていたコンテンツが徐々に順位を落としていくでしょう。低評価のコンテンツは、ますます順位が下がる可能性も考えられます。
そのため、記事完成後も加筆・リライトなどのメンテナンスを継続的に行うことが重要です。アルゴリズムやユーザーニーズの変化に合わせて手を加えていき、コンテンツの独自性・価値をさらに向上させていくことが、検索順位の上位表示につながります。
コンテンツSEOを実施する際に留意すべきポイントとは
コンテンツSEOにおける重要点は、検索エンジンのガイドラインや方針に沿った施策を行うことです。
ただし、ルールを守った記事を書くだけでは、競合が多い場合に思うような成果を得られません。
ガイドラインや検索エンジンの方針を理解することに加えて「狙ったユーザーがアクセスしてくれる」コンテンツに仕上げることも大切です。
Googleが重視しているコンテンツの質を参考に、記事制作時に留意すべきポイントをご紹介します。
ユーザーの利便性を最優先に考えて作る
ユーザーが検索エンジンを介してコンテンツに辿り着いたとき、重視しているのは自分の悩みや疑問を解消してくれる利便性です。アクセスしたウェブサイトやコンテンツに有益な情報がなければ、利便性を感じることはありません。
ユーザー目線でコンテンツを作成すると、自然検索からの流入が増えるだけではなく、滞在時間を伸ばしたりリピーターを増やしたりする効果が期待できます。
自分にとって有益な情報が多いと分かれば、同じコンテンツやウェブサイトをじっくり閲覧するために、滞在する時間が伸びるものです。後日同じコンテンツにアクセスすることもあるでしょう。
また、記事の質だけではなく、スマホ画面に対応させたり、ページの表示速度を上げたりすることも、ユーザーの利便性を左右するポイントです。
多くの流入があるうえ、同じユーザーが長時間滞在やリピート訪問しているコンテンツは、検索エンジンから利便性の高さを評価されます。評価が高くなれば、コンテンツが上位表示されやすくなります。
検索順位を上げるための不正行為を行わない
検索順位を上げるために、Googleが不正行為ととらえるようなSEO対策を行うことは避けましょう。いわゆるブラックハットSEOを意図的に取り入れないことはもちろん、無意識のうちに不正行為にあたる施策をしないことも重要です。
Googleが公式に不正行為の例としてあげているのは、下記のとおりです。
・コンテンツの自動生成
・リンク プログラムへの参加
・オリジナルのコンテンツがほとんどまたはまったく存在しないページの作成
・クローキング
・不正なリダイレクト
・隠しテキストや隠しリンク
・誘導ページ
・無断複製されたコンテンツ
・十分な付加価値のないアフィリエイト プログラムへの参加
・ページへのコンテンツに関係のないキーワードの詰め込み
・悪意のある動作を伴うページの作成
・構造化データのマークアップの悪用
・Google への自動化されたクエリの送信
Googleがあげる不正行為の中には、ブラックハットSEOに分類される故意の行動に加え、スパムやハッキングといった第三者からの悪質な行為も含まれることが特徴です。定期的なウェブサイトのメンテナンスで各コンテンツのスパムやハッキングを削除し、不正行為で検索順位が下げられないよう対処しましょう。
サイトの独自性・価値をどうすれば出せるか工夫する
検索エンジンの評価を上げるためには、競合にはない独自性や価値を与えることが重要です。
たとえばユーザーが商品紹介ページにたどり着いたとき、求めているのは特定の商品・サービスのスペックや評判です。知りたい部分について記載されておらず、「詳しくはお問い合わせください」と連絡先だけが表示されている状態は、利便性が高いとは言えないでしょう。
商品・サービスの評判を伝えるなら、利用者の声を取り入れたり、自社が生産にかける想いや実施している取り組みを紹介したりするコンテンツが適しています。
ユーザーは何を求めているのか、どのようなコンテンツがあると利便性を高められるかを念頭に置き、独自性や価値を追及することが重要です。
検索結果画面に何が表示されているか事前に確認する
作成したコンテンツは記事そのものの品質に加えて、検索結果でどのように表示されるかも確認しましょう。
検索結果によっては、ナレッジパネル(検索結果の右側に表示される情報ボックスのこと)が表示され、Webページを開いてもらえないことがあります。
ユーザーがナレッジパネルの情報のみで満足してWebページにアクセスしてくれない事態を避けるためには、狙っているキーワードの検索結果をあらかじめチェックすることが大切です。
検索結果で何が表示されているか確認したうえで、狙うキーワードを絞り込みましょう。
公開で終わりではなく、継続的なメンテナンスが必要
検索エンジンの評価基準や順位は、常に変わっていくものです。
Googleも大々的なコアアップデートはアナウンスする一方で、日常的に行っている小規模なアップデートに関してはこまかなアナウンスを行っていません。
さらに、ガイドラインに違反しているWebサイトなどは目視でも対処されています。以前は問題なかったとされる手法も、アップデートによって違反行為となるおそれがあります。
よってコンテンツを公開した後も、継続的なメンテナンスが不可欠です。常にサイト内のコンテンツを最新のルールや評価基準に合わせて改修していくことが、コンテンツSEO施策のコツです。
継続的なメンテナンスは、コンテンツの利便性を向上させる効果も期待できます。
例えば、特定のサービスに関して紹介する記事の場合、ユーザー数や満足度などの情報は、可能な限り新しいものを使用したほうが説得力は高くなります。
ユーザーの利便性を向上させ、コンテンツの信頼性を維持するためにも、公開した後の記事はこまめに確認・メンテナンスしましょう。
ボタンの位置や内部リンクなど、構造面もユーザー動向を参考に改善すると、より洗練された記事に仕上がります。
まとめ
近年の検索エンジンは、ユーザーの利便性を重視したアルゴリズムのもと、コンテンツの順位を決定しています。そのため、丁寧な記事作りによって検索エンジンの評価を上げ、正攻法で上位表示を狙うコンテンツSEOに注力する企業が増えつつあります。
しかし自社に専門チームやノウハウが存在しない企業の場合、コンテンツSEOは何から始めれば良いのか分からないケースも多いのではないでしょうか。
未知株式会社は、さまざまな手法で多くの企業様のコンテンツマーケティングをサポートしております。
ホワイトペーパーにて集客や採用などの課題解決事例についても紹介しておりますので、あわせてご活用ください。