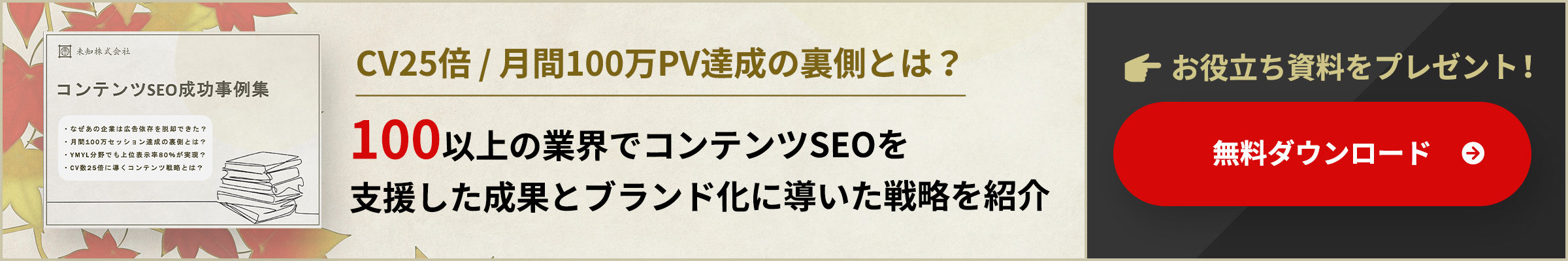目次
BtoBにおけるSEOの役割・相性
BtoBマーケティングにおけるSEOの役割は、見込み顧客が自社の商品やサービスをWeb上で見つけやすくし、リード獲得やナーチャリングに繋げることです。BtoB領域では、見込み顧客を契約や購買までに繋げるのに時間がかかるため、長期的な戦略が不可欠です。
その点で、SEOは中長期的な施策において非常に相性が良く、効果的な手段といえます。ここでは、BtoBマーケティングにおいてSEOがどのように機能するかを解説します。
BtoB特有の長期的な検討期間
BtoBでは、ユーザーが契約や購買に至るまでの検討期間が長く、多くの情報を収集しながら意思決定を行うことが一般的です。そのため、マーケティング戦略は短期的な効果を狙うだけではなく、長期的な視点で進める必要があります。
この点で、SEOは非常に有効な施策です。例えば、顧客管理システムの導入を検討している企業は、まず「顧客管理システム 導入 効果」や「CRMシステム 比較」などのキーワードで情報を検索することが多いです。
SEOを活用することで、こうした検索結果に自社のコンテンツを表示させ、見込み顧客が検討段階で自社の存在を認識し、興味を深める機会を生み出します。
意思決定に必要な情報収集
BtoBでは、顧客が契約・購買に至る前に多くの情報を収集することが必要です。担当者が決裁者に提案する際に「事例」や「システムの使い方」、「費用対効果」などの情報を丁寧に調べ、慎重に判断を下す必要があります。
この際、SEOは重要な役割を果たします。例えば、顧客が「事例」や「システムの使い方」、「費用対効果」などを検索したときに、自社のコンテンツが検索結果で上位に表示されるようにすることがSEOの目的です。
見込み顧客は自社が提供する情報に触れることができ、その内容を通じて自社のサービスや製品に対する興味や関心が高まります。このプロセスを通じて、最終的に購買決定を行う際に、自社が有力な選択肢として浮かび上がることが期待されます。
BtoB企業のSEO戦略/戦術
BtoB企業がSEO対策を成功させるポイントには、以下の5つがあげられます。
| ・SEOを注力すべきWebページを整理する ・カスタマージャーニーマップを作成する ・ユーザーフェーズに合った検索キーワードを選ぶ ・コンバージョンポイントを最適化する ・PDCAサイクルで施策をアップデートし続ける |
それぞれ詳しく説明します。
SEOを注力すべきWebページを整理する
BtoB向けのSEO戦略では、限られたリソースを最大限に活用するために、まずは自社サイトのページ種別ごとの役割を理解し、SEOに注力するページを決定することが大切です。
BtoB企業のサイトには、以下のような種類のページがあり、各ページが持つ役割に応じて、SEO対策を行うべきページを絞り込むことが必要になります。
| ・トップページ ・サービスページ ・リクルート情報 ・会社概要 ・オウンドメディア(コラムページ) |
特に、顕在層へのアプローチが可能なサービスのトップページと、潜在層を引き込むオウドメディアのページに重点を置くことが、SEOでの成果を最大化するためのポイントとなります。
サービス・トップページ
サービスページ(またはランディングページ)は、BtoB企業においてCVに最も近いページのため、優先的にSEO対策を行うことを推奨しています。
サービス名やサービスカテゴリ名での上位表示を狙い、顕在層のリードを獲得するために有効です。例えば、時間管理システム「TimeCrowd」は、以下のような具体的なキーワードで上位表示されています。
| ・サービス名:タイムクラウド(1位) ・サービスカテゴリ:時間管理 クラウド(1位) ・サービスカテゴリ:時間管理 ツール(2位) ※2025年6月時点 |
このように、サービスページやサービスサイトでは「サービス名」や「カテゴリ名」を中心に上位表示を目指すことで、「今すぐ導入を検討したい」という顕在層のアクセスを増加させることができます。
オウンドメディア(コラムページ)
オウンドメディア(コラムページ)では、サービスページで対策しにくいキーワードに対して柔軟に対応できるため、SEO戦略において欠かせません。
先程の時間管理システム「TimeCrowd」では、以下のようなキーワードで上位表示されています。
| ・時間管理 エクセル(1位) ・タイムログ とは(1位) ・工数不足(1位) ※2025年6月時点 |
オウンドメディア(コラムページ)のSEOを強化することで、今すぐの購入を考えていないものの、課題や疑問を抱えている準顕在層や潜在層を引き込むことができます。
このように、BtoB向けのSEO戦略では、限られたリソースを効率よく活用するために、事前にどのページを最適化させるのか設計を行うことが大切です。
カスタマージャーニーマップの作成
サイト全体の戦略を立てた後、ターゲットがサービスの認知から情報収集・比較検討を経て購入に至るまでの行動や心理を、各フェーズに分けて具体的にイメージすることが重要です。
ペルソナが曖昧でターゲットの行動や心理を分析せずに幅広い層からのアクセスを集めても、効果的なアプローチができず、契約や購入にはつながりにくい可能性があります。
イメージを具体化するためには、各フェーズにおける行動や心理をカスタマージャーニーマップとして一枚の表に詳しく書き出す手法が効果的です。
例えば、情報収集段階のユーザーは、自社の課題解決に役立つツールの機能や相場などを調べていると考えられます。こうしたユーザーには、オウンドメディアのコラムページやホワイトペーパーなど、役立つ情報を提供するコンテンツでタッチポイントを作ることが効果的です。
また、各フェーズに適した施策を実行するために、KPIを設定することが大切です。例えば、サイトのPV数やホワイトペーパーのダウンロード数など、具体的なKPIを設定することで、施策の効果を検証しやすく、改善点を把握することができます。
ユーザーフェーズに合った検索キーワードを選ぶ
ユーザーフェーズとは、顧客が商品やサービスに関してどの段階にいるかを示す概念です。ユーザーの行動や心理状態を理解し、適切なタイミングで必要な情報を提供するために、購買の過程をいくつかのフェーズ(段階)に分けて考えます。
SEOで集めるユーザーの質は、どのキーワードを選ぶかによって大きく左右されます。そのため、検索キーワードはサービスの購買プロセスを意識しながら、ターゲットに関する情報をもとに慎重に検討することが重要です。
基本的には、「今すぐ導入や購入を検討している顕在層」を狙ったキーワードから優先的に対策するのが効果的です。例えば、「サービス名」や「○○システム」といったカテゴリ名など、具体的なニーズを持った検索に対応できるキーワードが該当します。
すでにサービス名やカテゴリ名で上位表示を獲得できている場合は、次の段階として「特定のサービスは決まっていないが、導入を検討している準顕在層」に向けたキーワードを選びましょう。
例としては、「顧客管理 システム 比較」「顧客管理ソフト おすすめ」などがあり、これらのキーワードを軸にオウンドメディア(コラムページ)でSEO記事を展開することで、準顕在層とのタッチポイントを作ることができます。
自社にとって、適切なキーワードを選定するためには、営業担当者へのヒアリングや商談のログ、業界紙から顧客が抱える悩みを洗い出し、ターゲットのニーズを明確にすることが大切です。
コンバージョン(CV)ポイントを設計する
ページごとの役割に応じて適切なコンバージョン(CV)ポイントを設計することが重要です。
コンバージョンポイントとは、ユーザーにアクションを促すための導線や仕掛けのことです。例えば、「見積もり・問い合わせ」「資料請求」「ホワイトペーパーダウンロード」などがそれにあたります。
ただし、ユーザーの関心度や検討段階(=ユーザーフェーズ)に合っていないCVポイントを設定すると、ページへのアクセスはあっても成果にはつながりません。そのため、ユーザーフェーズを意識した設計が欠かせません。
潜在層・準顕在層向けのCVポイント
比較的ハードルが低く、ユーザーにとって行動しやすいCVポイントが適しています。
・ホワイトペーパーのダウンロード
・メールマガジン登録
・セミナー申し込み
顕在層向けのCVポイント
購買意欲が高いユーザーには、成約に直結するようなアクションを促しましょう。
・サービス資料請求
・お問い合わせ
・デモ体験申し込み
・見積もり依頼
また、CVポイントは「配置や表現」も重要です。例えば、ボタンの文言を「無料で資料を見る」にするだけでもクリック率が上がることがあります。また、目を惹くデザインや自然な導線配置にすることで、ユーザーの行動を後押しできるでしょう。
PDCAサイクルで施策を継続的に改善する
SEO施策でより高い成果を上げるには、定期的な効果測定と改善の繰り返し=PDCAサイクルを実行し、コンテンツや導線を継続的にアップデートしていくことが重要です。
SEOの最適解は業界や企業によって異なるため、一度作って終わりではなく、実行しながら仮説を検証・修正する柔軟な姿勢が求められます。
具体的なPDCAの回し方
・Plan(計画)
上半期に「問い合わせ数を前年比20%増やす」という目標を設定し、それに向けて新規コンテンツの作成やCV導線の強化を計画。
・Do(実行)
記事公開、タイトルや構成の調整、CTAボタンの追加など、具体的な施策を実施。
・Check(評価)
GoogleサーチコンソールやGoogle Analyticsを活用し、流入キーワード、掲載順位、CV数、直帰率などを定期的に確認。
・Act(改善)
例えば、アクセスは多いが問い合わせが少ない場合、コンテンツの訴求内容やCVポイントがユーザーのニーズに合っていない可能性があります。競合との比較や営業チームからのフィードバックを活用し、内容を調整・更新しましょう。
チーム連携も重要
改善すべきポイントはWebコンテンツだけに限りません。例えば、営業チームとの連携フローやフィードバック体制を見直すことで、より成果に直結する改善策が見えてくることもあります。
SEOは一度の施策で完結するものではなく、継続的な試行錯誤を通じて完成度を高めていく取り組みです。PDCAを意識した運用体制を構築し、成果につながるSEO施策を行いましょう。
BtoB企業がSEO対策に取り組むべきか判断する方法
SEOはBtoB企業にとって有効な集客手段のひとつですが、すべての企業に適しているとは限りません。業界の特性や自社の体制によっては、SEOに取り組んでも効果が出にくいケースもあります。ここでは、BtoB企業がSEO対策に取り組むべきかどうかを判断するためのポイントを解説します。
ターゲットが検索行動をとる傾向にあるか調査する
まず確認すべきは、ターゲットとなるユーザーがインターネットで情報を検索する傾向にあるかどうかです。
もし、業界内での情報収集手段が展示会や専門誌、口コミなどオフラインに偏っている場合、Web検索からの流入は期待しにくく、SEOの効果も限定的になります。
ターゲットの検索行動の傾向を知るには、自社商品や関連サービスに関する検索キーワードの検索ボリュームを調査する方法がおすすめです。また、自社の顧客がどのように自社を知ったかについて、アンケートやヒアリングを行う方法も検討しましょう。
判断する際は、以下の方法がおすすめです。
| ・自社の商品・サービスに関連する検索キーワードの検索ボリュームを調べる ・既存顧客へのアンケートやヒアリングで、どのように自社を知ったかを確認する |
これらを調べると検索経由での情報収集がターゲットにとって有力な手段かどうかを把握できます。
長期的にSEOに取り組めるか検討する
SEOは短期的な成果が出にくい施策であり、コンテンツの継続的な発信や改善が不可欠です。一度ページを作って終わりではなく、情報の更新や検索ニーズの変化に合わせて修正を加える運用体制が求められます。
そのため、以下の点を事前に確認しましょう。
| ・自社にコンテンツ制作や改善を継続できるリソースがあるか ・担当者のスキルや工数は足りているか ・難しい場合は、外注先の活用も含めて検討できるか |
特にBtoB領域では、信頼性や専門性が求められるため、情報の正確性や品質維持が非常に重要です。長期的にコンテンツ品質を維持・強化できる体制が整っているかを見極めてから、SEOへの取り組みを判断しましょう。
実際のBtoB企業のSEO成功事例
BtoB企業である当社・未知株式会社でも、SEOを活用して実際に成果を上げた事例をご紹介します。
広告費の高騰と低い知名度が課題
当社は、もともとコンテンツマーケティング支援を事業の柱としており、新規リード獲得の多くをWeb広告に依存していました。しかし、広告費の高騰により費用対効果の悪化が課題となっていました。
また、当時の弊社には「記事作成会社」という限定的なイメージが強く、「コンテンツマーケティング、Webマーケティング全体を支援できる会社」としての認知が弱いという問題も抱えていました。
オウンドメディアを活用したSEO強化
この課題を解決するため、私たちはオウンドメディアを軸にSEO施策を本格的にスタート。戦略的に「コンテンツ」や「コンテンツマーケティング」などのブランド系キーワードを狙ったコンテンツ制作を行いました。
単なる記事情報にとどまらず、
・自社サービスの理解促進
・コンテンツマーケティングの価値の浸透
・「記事作成会社」から「コンテンツマーケティング支援会社」への印象転換
を目的として、記事構成・導線設計を工夫しました。
上位獲得&広告費の削減に成功
結果として、開始からわずか3カ月で「コンテンツ」「コンテンツマーケティング」などのブランドワードで検索順位1位〜2位を獲得。この成果により、以下のような具体的な変化が生まれました。
| ・オウンドメディア経由のリード獲得数が大幅に増加 ・昨年度Web広告費を3分の1削減に成功(リード数は維持) ・SEOによる継続的な集客が可能となり、広告依存からの脱却に成功 |
本格的に取り組み始めたのは比較的最近(2024年頃)でしたが、適切な戦略とコンテンツ設計によって後発でも結果を出すことが可能であると実感しています。
まとめ
BtoB企業にとって、SEOは見込み顧客の検討フェーズに応じて最適な情報を届けられる、効果的なマーケティング施策です。SEO対策を成功させるには、ターゲットの心理や行動プロセスを丁寧に分析し、それに基づいたキーワード選定やコンバージョン導線の設計が欠かせません。
自社のサービスと検索行動との親和性が高い場合は、SEO施策の強化によって新たなリード獲得や商談機会の創出につなげることが可能です。
<無料資料>
顧客満足度96%!未知のSEOコンサルティングとは?